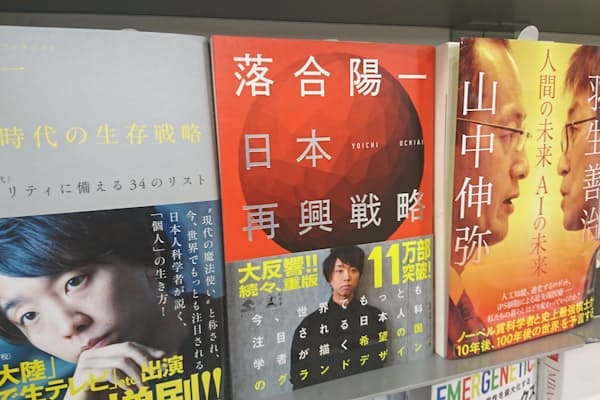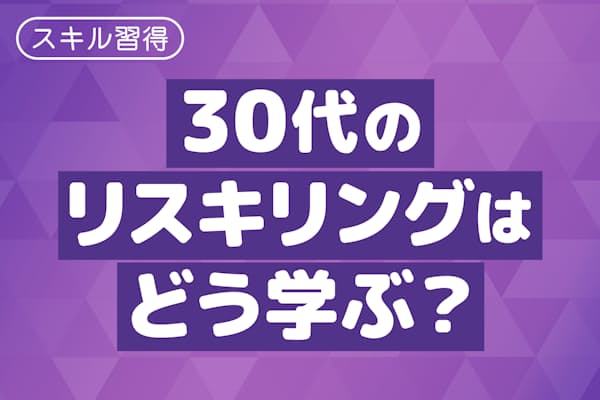クジラ研究で鍛えた交渉力 凄腕コンサルの筑波大時代
本徳亜矢子アクセンチュア・マネジング・ディレクターが語る(上)

本徳亜矢子アクセンチュア マネジング・ディレクター
有力企業の人事担当者が選ぶ「採って良かった大学ランキング」(大学イメージ調査・2018年、日本経済新聞社・日経HR)で、1位に輝く筑波大学。高評価の原因はどこにあるのか。筑波大出身で、人材育成や組織改革のコンサルティングなどが専門の本徳亜矢子アクセンチュア・マネジング・ディレクター(43)が、自身の大学時代を振り返りながら、筑波大の校風や強みを語った。
みんなジャージー姿で大学に通っていた。
筑波大は、東京や大阪などの大都市から遠く離れたいわゆる田舎の国立大学。ふだんは他の大学の学生と交流する機会もほとんどないので、やはり都会の大学にはない独特のおおらかさがあったと思います。
学生は全国から集まってきますが、大半の学生は1年生の間は寮生活。2年生になると寮を出て、大学周辺のアパートを借りて自活を始めます。
これも都会の大学ではあり得ないことですが、ジャージー姿で学校に来る人が結構いました。周りもみんなジャージーなので平気です。私はジャージー姿ではありませんでしたが、おしゃれとは無縁の格好で通学していました。
最近、リクルーターを兼ねて、毎年、母校を訪れていますが、昔に比べるとみんな、すごくおしゃれになりました。ジャージー姿もほとんど見かけません。
ただ、外見は変わっても、中身の気質はそれほど変わっていないように思います。仕事で筑波大学の後輩に会うこともありますが、東京の私立大学出身者と比べるとマイペース型が目立ちます。でも、これはおそらく筑波だからというわけではなく、地方の国立大出身者に共通の特徴ではないかと思っています。
こんなふうに、筑波大学は都会の大学に比べるといろいろな面で変わっていましたが、私が籍を置いていた文化人類学の研究室は、それに輪をかけて変わっていました。