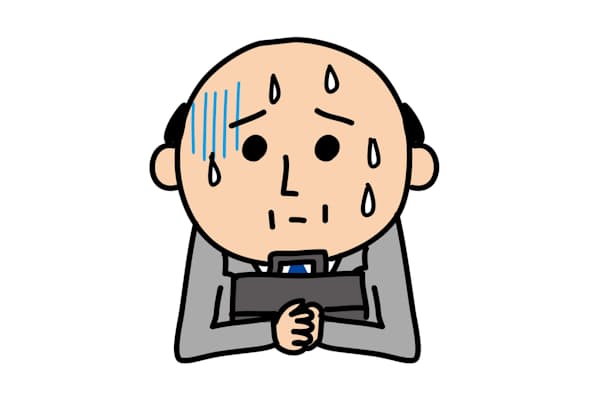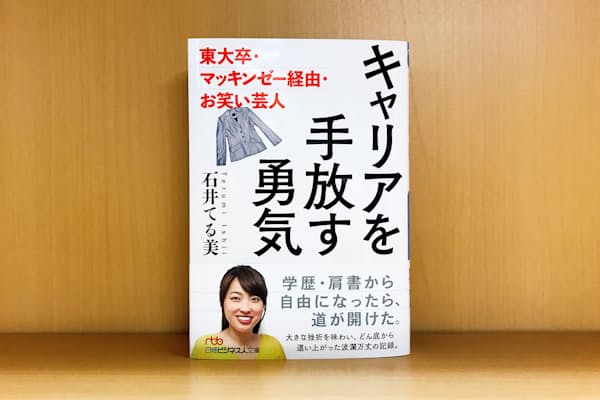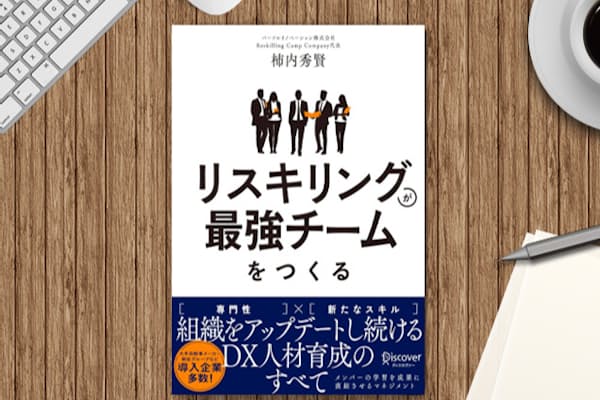元マッキンゼー芸人 プロ分析と笑い台本に共通点
東大卒お笑いタレント 石井てる美氏

「フリオチと比較分析は似ている」と話す石井てる美さん
マッキンゼー・アンド・カンパニーで働いた経験を持つお笑いタレントの石井てる美さんが、コンサルティングとお笑いに共通するスキルなどを紹介する連載。今回はコンサルに必須の比較分析手法と、笑いを生むフリオチが似ているという。どういうことか。
◇ ◇ ◇
フリがなければオチは成り立たない
お笑い養成所に入りたての頃、お笑いのネタを作って披露する授業でのことです。芸人がネタ見せをすると直後にフィードバック(通称ダメ出し)をもらうのが常なのですが、あるとき講師の放送作家の先生にこう言われました。「フリが無いんだよ、フリが!」
当初、私はこの「フリが無い」の意味が分かりませんでした。お笑いを始めたばかりの頃の私は、笑いとは「ただおかしなことをすればいい」と思っていた節があり、笑いを生むメカニズム「フリオチ」「裏切り」を理解していなかったのです。そのときにやったネタも「クビを宣告された社員が上司の前でギャグを繰り広げていく」という今思うとむちゃくちゃなコントで、そのときは「ただギャグをしたい」「ボケたい」というオチの部分しか頭にありませんでした。
フリとはオチの引き立て役で、相手に「この先こうなるんだろうな」と想定させたり、この先に起こることに対しての期待をあおったりします。そして、オチで意外な結末を用意して相手の予想を裏切ったり、はたまた、ふに落ちることが起きたりすると、笑いが生まれ、見ている人を魅了する現象となります。
「なぜ、あなたの話はつまらないのか?」(美濃部達宏著)では、フリオチは打ち上げ花火に例えられています。導火線に火がつき、ヒューと音を立てるまでが「フリ」、火薬に引火してドーンと花火が打ち上げられるのが「オチ」です。フィギュアスケート鑑賞が大好きな私としては、フィギュアスケートのジャンプもまさにフリオチだと思っています。「フリ」の助走の部分で観客の期待と緊張が極限まで高まり、「オチ」のジャンプが決まると「待ってました!」とばかりに見ている者の感動が爆発するのです。