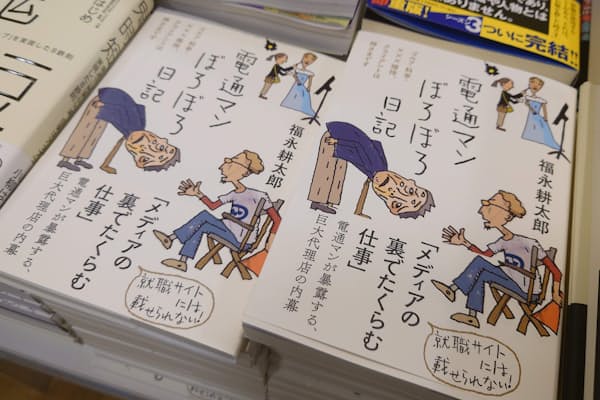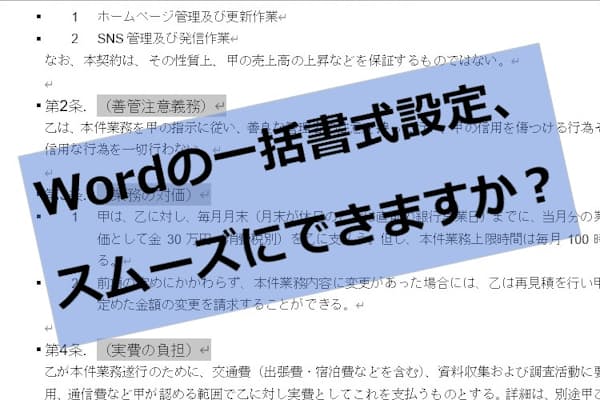カリスマ再生請負人、原点は創業した会社のリストラ
経営共創基盤の冨山和彦CEO(上)

経営共創基盤の冨山和彦最高経営責任者(CEO)
カネボウやぴあなど、数多くの企業再生に携わり、「カリスマ再生請負人」といわれる冨山和彦・経営共創基盤最高経営責任者(CEO)。その経歴は、東大在学中に司法試験に合格、名門ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)を経て独立という華麗なるものだ。しかし、「経営リーダーが自分の天職」と感じたターニングポイントは、30代での挫折経験だったという。「頭が良ければ経営できるわけじゃない」。その真意とは。
父の影響で意識した「プロ経営者」の道
――在学中に司法試験に合格しながら、なぜ新卒でコンサルタントの道を選んだのでしょうか。
「サラリーマンになりたくなかったんですよ。父親はもともと江商という商社に勤めていて、オーストラリアのパースに住んでいた。ところが、昭和40年不況で経営危機に陥って、僕が小学校2年のときに兼松に吸収されたんです。事実上、つぶれたんだよね。江商って、上の世代からすると名門商社なんです。でも、そういう会社もつぶれるんだなと。父はしばらくして会社をやめ、雇われ経営者のようなことをやっていた。だから、父の影響もあって、『サラリーマン的な価値観』について、冷ややかなところがありましたね」
「食べていくために行きたくないゴルフに週末行くのも嫌だし、気に入らない上司におべっかを使うのも嫌。要は生意気だったんです。サラリーマンになりたいとは思わなかった。そうすると、東大法学部だから、司法試験を受けるのが一番自然だろうと。そもそも、東大だって青雲の志があって行ったわけじゃない。文系で一番、偏差値が高くて、ほぼ受かりそうだったからです(笑)」
「ところが当時、就活の解禁は4年生の8月だったんだけど、司法試験の発表は11月だった。だから、就活しようと思えばできてしまう。実は、すでに法律の勉強に飽きていた(笑)。基本的に飽きっぽいんです。そこで、採用を始めたばかりの投資銀行やコンサルティングファームを受けました。ほかは落ちたんだけどBCGだけ内定をもらうことができた。コンサルティング企業はあくまでプロ集団で、サラリーマン型組織じゃないですからね。そのまま、BCGに入社しました。私の人生は基本、行き当たりばったりなんです」
帰国して味わった挫折 「自己破産も覚悟した」
――その後、1年足らずでBCGを離れ、コーポレイトディレクション(CDI)の創業メンバーとして独立。留学もし、挫折の経験はないようにみえます。
「ありますよ。一番の挫折はね、自分が創業した会社をリストラしたことです。CDIは、BCGのメンバーが分かれて創業した会社でした。バブルの頃だから調子もよかった。翌年には新卒の採用も始めて、創業4、5年で70人くらいの規模になった。ちょうど経営を本格的に勉強したいと思っていたので、願書に『自分はアントレプレナーだ』と書いて米スタンフォード大の大学院を受けて合格。経営学修士号(MBA)を取得して、意気揚々と帰ってきたらどん底が待っていた。バブルが崩壊して、社員は半分に減りました。私の再生案件第1号は、自分が創業した会社なんです」