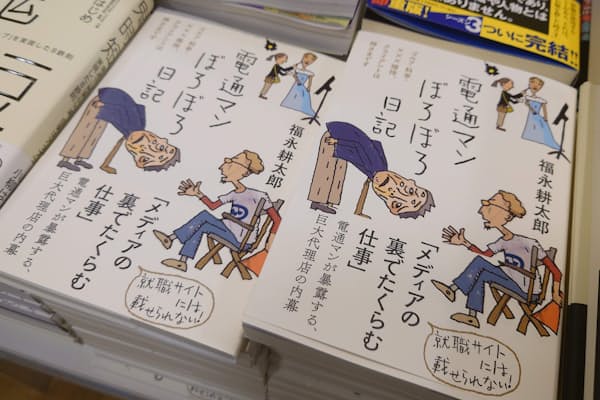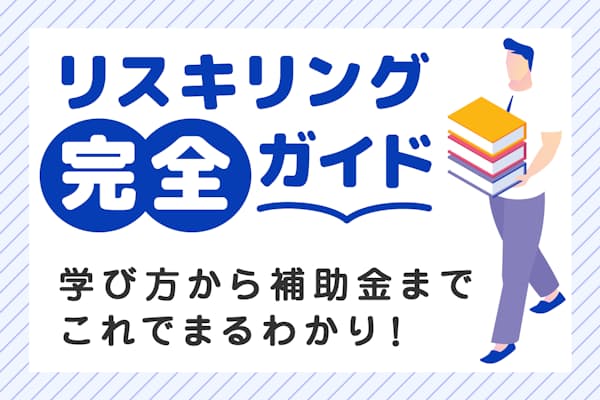「家事が苦手」な富士通元SE 逆手に挑む代行シェア
タスカジ 和田幸子社長(上)

「一時は夫婦そろって家事を放棄してしまった」と、子どもが保育園に通っていた時期を振り返る和田幸子タスカジ社長
共働き夫婦にとって頭の痛い問題が、家事・育児の分担だ。そんな状況を改善したいと、富士通を飛び出し、起業したのがタスカジの和田幸子社長。手軽に格安で家事代行サービスを利用できるマッチングサイトを運営している。家事の苦手な和田氏が目を付けたのがインターネットを介し、スキルの高い「外の人」と家事をシェアするという意味で「シェアリングエコノミー」とも呼ばれる事業を立ち上げた。個人間取引の新ビジネスと注目を集めている。
◇ ◇ ◇
横浜国立大学で経営学を学んでいたころは、キャリアについていろいろな選択肢を思い浮かべていました。在学中に男女雇用機会均等法が改正され、女性がもっと社会へ出て働く時代になるだろうとは思っていましたが、起業なんて、ほんの一握りの勇気ある人たちがすることだと思っていました。
そんなある日、大手メーカーを退職し、50歳代でコンサルティング会社を立ち上げた人の本をたまたま読みました。会社員時代の経験を基にしてこんなふうに起業する方法もあるのだなと、とても新鮮に感じたのを覚えています。
富士通に入社し、会計システムの開発を担当
1999年に大学を卒業し、システムエンジニア(SE)として富士通に入社しました。担当したのは会計システムの開発です。金融ビッグバンに伴い、企業の情報公開が強く求められるようになり、国際的な会計基準に合わせた法改正が始まった時期でした。
職場はとても忙しく、混沌としながらも、活気にあふれていました。MBA(経営学修士)を取得するために大学院に行こうと思ったのは、開発に携わって数年経ったころのことです。もともと新規事業の立ち上げに興味を持っていて、社内でもそれを担える人材になりたかったのですが、SEという仕事では経営戦略やマーケティング戦略に触れる機会が少なく、もう少し経営者の視点に立った見方ができるようになりたい、と思ったのです。
今でこそ社会人になってから大学院で学び直す人は珍しくありませんが、当時は社内に留学派遣制度があっても、誰もが大学院へ行きたいという感じではなかったように思います。出世したければ、現場で経験を積むほうがいい。そう考える人が大半でした。目の前の課長に昇進するという意味でなら、実際、そのほうが早かったと思います。
それでも会社の規模が大きかったこともあってか、全体ではそれなりの希望者が集まり、1年目は社内選抜を通りませんでした。2度目の枠で選抜を通り、慶応義塾大学大学院経営管理研究科へ。海外で学ぶことも考えましたが、英語がそれほど得意ではなかったことと、「日本語のほうが深く学べる」とアドバイスしてくれる先輩もいたので、国内で学ぶことを選びました。