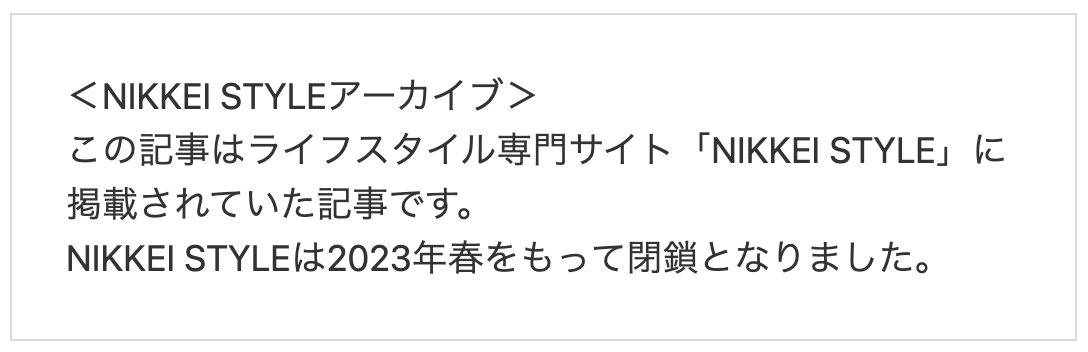VERBAL なぜ米エリート証券マンからラッパーに?
編集委員 小林明

2016年末、北海道での交通事故で瀕死(ひんし)の重症を負い、死の淵から生還した人気ミュージシャン、VERBAL(バーバル)さん。米名門ボストン・カレッジを卒業した後、勤めていた証券会社スミス・バーニーを依願退社し、やがてラッパーとして音楽活動を開始。現在では音楽プロデュースやDJ、服飾デザインなども手がける人気クリエーターとして活躍を続けている。なぜエリート証券マンのキャリアを捨ててまでラッパーになったのか?
前回「人気DJ、VERBAL 死の淵から生還して学んだこと」に続き、VERBALさんの独占インタビューの後半を紹介する。
小5の夏に米国でヒップホップに衝撃、漫画家目指した少年時代
――最初に音楽と出会ったのは米国だったそうですね。

「そうです。小学校5年の夏に母親とボストンに行き、現地のサマーキャンプに参加したときにものすごい衝撃を受けました。同世代の子どもたちがナイキのジャージーやスニーカーを履き、金のネックレスを付け、ロボットみたいなカクカクした動きでブレイクダンスを踊っているんです。ラジカセを担いでヒップホップグループ、RUN-DMC(ラン・ディーエムシー)の曲をかけながらラップを口ずさんでいた。そんなの生まれて初めて見たのでビックリしました。『なんて格好いいんだろう』と思ったのがすべての出発点です」
――VERBALさんはどんな子どもだったのですか。
「東京の目黒で育ったのですが、僕はおかっぱ頭にアニメのTシャツを着て、半ズボンに『電子戦隊デンジマン』のズック靴を履いていた。

『ドラえもん』ののび太くんみたいな格好をしていたんです。どこにでもいるような小学生でした。小3のときにアニメ『北斗の拳』が始まり、ロボット玩具『トランスフォーマー』やミニ四駆で遊び、キン肉マン消しゴム(キン消し)を集めていた世代。ファミコンの『ポートピア連続殺人事件』や『ドラゴンクエスト』にも熱中していました。当時の僕は『ドラゴンボール』など鳥山明さんの漫画が大好きで、将来は漫画家になろうと夢見ていた。自分でスクリーントーンを買って来て、自作漫画を描いて友人に見せたりしていた。そんな無邪気な少年に突然、米国のヒップホップ文化が飛び込んできたわけです」
オーディション番組でいきなり優勝、「ラップでは食えない」とデビューを断念
――それは大きなカルチャーショックですね。

「『ラップ音楽って、言葉をしゃべっているだけなのに歌として成立しているんだ』なんて驚いて、興味を持ったのを覚えています。まだインターネットがなかったので、米国のヒップホップの専門雑誌を定期購読するようになり、自分なりに最新情報を一生懸命に集め始めた。タワーレコードにもヒップホップのコーナーが少ししかなかったころの話です。やがて高校に入ったあたりから歌詞を書き始め、現在のm‐floのメンバーである☆Taku Takahashiとバンドを組みます。そこで初めて人前でラップをするようになったんです。☆Takuは小学校からの同級生で、早い時期からシンセサイザーで音楽を作っているクリエーティブな人間でした。音楽を一緒にやっているうちに、ある日、テレビのオーディション番組に挑戦しようと思い立って、試しにデモテープを送ってみたらすんなりと合格。そのまま出場して一気に優勝してしまったんです」
――いきなり優勝ですか。すごい勢いですね。

「レコード会社から契約のオファーも受け、夢が大きく膨らみかけたのですが、両親から猛反対されました。『ラップで食べていけるわけがないだろう』というわけです。僕も『まあ、そりゃそうだな』と一応は納得して、ミュージシャンとしてデビューする道を諦めました。両親には『弁護士でも医師でも何でもいいから、安定した職業についてほしい』といつも言われていたので、高校を卒業したら良い大学に進学して両親を安心させようと考えていた。ニューヨーク大学やボストン・カレッジに合格し、『ニューヨークに行ったら絶対に勉強しなくなるだろう』と両親に言われて、ボストン・カレッジを選んだのです」
両親を安心させようとボストン・カレッジへ、ニーチェやキルケゴールの哲学に熱中
――ボストン・カレッジでは何を勉強したのですか。
「経済学を専攻していて、さらに哲学の授業も受けたらすごく面白かったのでダブルメジャー(2つの専攻を履修)にしました。ものごとを難しく考えることが大好きで、哲学の論理的な思考に引かれたんです。熱中したのはニーチェやキルケゴール。難しい本を読んでいる自分の姿に酔っているようなところもあったと思います。大学卒業は1997年。インターンで大学4年生から働いてきた米証券会社スミス・バーニーにそのまま就職しました。世間的なイメージが良い会社なので、両親も喜ぶと思いました」
――名門大学を出て、エリート証券マンになったわけですね。
「ボストンの金融街で働きましたが、職場の雰囲気は独特でしたね。上司はベーグルを食べて、なぜかプラスチック製バットを振りながら、バリバリ仕事をしている。業績が上がるたびにフロア全体がウォーと盛り上がって、『よし、今夜は飲むぞー。イェー』なんてイケイケムードになっている。レオナルド・ディカプリオが主演した映画『ウルフ・オブ・ウォールストリート』みたいな世界でした。でも、僕はどうしても仕事に熱意や興味が持てなかった。両親を喜ばせることを優先して、自分の身の丈に合っていなかったんでしょうね。午後5時までの仕事でしたが、4時半ぐらいになると『早く5時になれ』と時計ばかり気にしているような社員でした。だからインターン期間も含めて1年も続かず、結局、会社を途中で辞めてしまいました」
エリート証券マンになじめず1年で退社、デビューのきっかけは☆Takuとのコラボ
――サラリーマン生活が合わなかったんですか。
「いいえ、サラリーマン生活が嫌いというより、自分のやりたいこと、パッションはなんだろうと考えるようになったんです。少し生意気ですけど、人のためにできる仕事とはなんだろうと。それで、とりあえずインターネットの会社に勤めたり、セールスの会社に勤めたり、神学校に行ったりしながら過ごしていましたが、たまたま日本に帰国した冬休みが人生の転機になりました。高校で一緒にバンドを組んでいた☆Takuが楽曲のリミックスを作っていて、『ラップやってよ』と久しぶりに誘われたんです。そこで高校時代の軽いノリで歌ってみたら、その曲のアナログ盤500枚があっという間に完売したと聞いてビックリしました。そんな調子で米国と日本を何度も行き来しているうちに、☆Takuと曲を作るようになり、m‐floの原型になっていきます」
――どういう歌詞を書いていたんですか。
「米国のラップの歌詞を聞いていると、黒人として米国に生きる意味とは何かとか、政治的な背景を強く打ち出している。RUN-DMCやクール・モー・ディー、パブリック・エナミーもみんなそうです。僕は黒人ではないけれど、自分だったらこう書こうかなという方向で書いてみると、自然にペンが進み、歌詞が書けるようになりました。最初は、俺は格好いいぜとか、人種差別はよくないよねとかいう感じで、そこに女の子にモテたいみたいな気持ちが混在するというよくわからない歌詞を書いていました。リズム感があって韻を踏んでいれば何でもいいやという感じです。ちなみに高校時代の最初の作品は『リアル・ディール』と『アクト・オブ・スプレマシー(国王至上法)』。俺は本物だとか、俺の言うことには誰も逆らえないとか、そんな意味の大げさなタイトルの曲。なんだかダサくて恥ずかしいですね」
「m‐flo」「VERBAL」命名の由来は? 珍しかったアジア人ラッパー
――ついにm‐floとしてデビューします。

「当時の音楽事務所の社長から『絶対にデビューした方がいいよ』と熱弁されたんです。でも高校時代に僕は音楽の道を諦めていますから、やはり簡単には踏み切れません。アジア人のラッパーもほとんどいないし、『ラップで食っていくのは簡単ではないよな』とずっと思っていた。『デビューしてもすぐに売れなくなるんじゃないか』とやけに慎重になっている自分がいました。でも、曲が売れ始めると、日本での仕事が急に忙しくなり、結果として日本にずっといることになりました。最初に印税が入ったときには驚きましたね。まとまってお金が入ってくるという発想がまったくなかったんです。学費やローンを払った後、憧れていた15万円くらいの金のネックレスをすぐに買いに行きました」
――なぜ「m‐flo」や「VERBAL」という名前にしたのですか。
「英語と日本語を混ぜた音楽はそれまでなかったし、どうせならインパクトがある名前にしたかった。そこで、宇宙から飛んできた隕石(いんせき)という英語の『meteorite』と『media』を組み合わせた造語に、流れるという意味の『flow』を付けた『mediarite‐flow』としてみた。しかし、音楽事務所の社長から『それでは長すぎるよ』と言われたので、『m‐flo』に変えました。あえて『w』を取ったのは単純に格好いいと思ったからです。一方、自分の名前の『VERBAL』は言葉で人に伝える仕事なのでそう付けました。ただややこしいのは、日本ではバーバル、米国ではヴァーボウ、韓国ではボボル、イタリアではヴェルバルなどと発音が国ごとにかなり違うこと。世界で通用しにくい名前なので、今更ながら少し後悔しています」
――英語は子どものころから不自由なく話せたんですか。
「小学校から高校まで東京のインターナショナルスクールに通っていたので話せました。ただ日本で話している英語はニュアンスやリズム感が多少違っていて通じないこともある。授業で習っている英語は実際に米国で話されている英語とは少し違うんです。特に黒人から『Yo!』などと話しかけられると、その勢いにこちらが負けてしまう。東部や西部、南部の間では文化の違いもあって、言葉の意味が理解できないことも結構ありました。しかもスラングだと何を話しているのかさっぱり分からない。だから、最初に耳が慣れるまでは大変でしたね。いまでも打ち合わせで特殊ななまりがある英語圏の人などと話していると、適当に相づちを打っていますが、半分くらいしか内容が分からないことがあります」
多様性のある世界の英語、日本・東京を活動拠点にする魅力とは?
――世界のあちこちで活動していますが、活動拠点としての日本や東京の魅力は何でしょうか。

「世界の中心と言ったら大げさかもしれませんが、日本のようにルールが多いのに、何でもありという国はとても少ないと思います。オタクという言葉が生まれたくらい、あらゆる分野のスペシャリストがひしめいている。アート界ではイラストレーターの空山基さんのようなすごい芸術家がリスペクトされているし、京都には長い歴史を持つ着物の職人さんもいる。美意識もクオリティーも高い。掘れば掘るほど深い。海外から戻ってくると、そういうすごさを改めて実感します。中国でも韓国でも、そこまで感じることはありません」
「東京・原宿の歩行者天国を歩くとよく分かりますが、昔はロカビリーのダンスを踊っている人もいれば、ブレイクダンスをしている人もいたし、いまではスケートボードをしている人もいれば、ゴスロリの格好している人もいる。まったくごちゃごちゃだけど、音楽もファッションも美術もすべてが混在する面白さがある。それが原宿のエネルギー。世界の多くのクリエーターがヒントや着想が欲しくて東京に頻繁に来ます。僕も東京で育ったので『格好良くて刺激的だったら何でもありじゃないか』という自由な発想がある。今後も自分のこういう部分は大切にしたい。そんな風土があるからこそ、日本ではユニークな文化が開花するのかなと感じています」
――今後、どういう方向を目指すつもりですか。
「この年齢までラップをしているなんて、まさか夢にも思っていませんでした。だから、そこに可能性を感じます。20歳代は目先のことを追っているだけで精いっぱい。最高のラッパーになろうということしか考えていなかった。30歳代はいろいろと起業して、ビジネスとかテクノロジーに興味が広がった。いまは誰に向かってクリエーションをしているのか、再び原点を問い直しているところ。クリエーティブなことにさらにドップリと漬かってみたい。好きなことに絞って仕事をしていれば、そこに広がりがあるし、もっと深い世界を追求できる。そんな気持ちで仕事をしています」
ラッパー、プロデューサー、DJ、デザイナー。1975年東京生まれ。東京・世田谷のセント・メリーズ・インターナショナル・スクールを経て、米ボストン・カレッジ卒(経済学・哲学専攻)。米証券会社スミス・バーニーなどに勤めた後、98年に音楽グループ「m‐flo」を結成し、「come again」「miss you」など多くの楽曲をヒットさせる。2014年にEXILEのリーダー、HIROさんの呼びかけでMAKIDAIさん、DJ DARUMAさんらとクリエーティブユニット「PKCZ(R)」を結成。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。