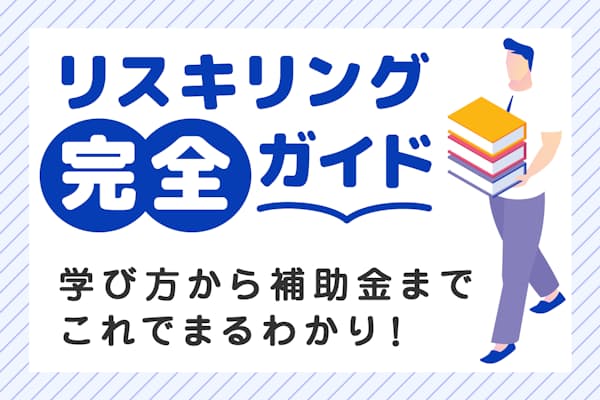「東大スパルタ受験校」を一新 海城の学校改革
海城中学高等学校の柴田澄雄校長に聞く

東京都新宿区大久保にある海城学園
中高一貫の男子私立校、海城学園(東京都新宿区)。東京大学の合格者数ベストテンに名を連ねる進学校だが、かつての「スパルタ受験校」というイメージを一新。受験秀才ではなく社会に出て活躍できる人材を育成するため、学校改革を次々断行した。2015年に三菱商事出身の柴田澄雄氏を校長として招き、新たにグローバル人材教育にも挑む。東京・大久保の海城を訪ねた。
元商社マン、招かれて校長に
「文化祭、彼女来るの?」
「来るわけないだろう。というか、彼女なんていないよ」
中国語や韓国語、ベトナム語が飛び交い、「アジアタウン」と呼ばれるJR新大久保駅周辺。9月13日の午後3時を過ぎると、冗談を言い合う男子中高生の集団が次々姿を現した。約2千人が通う海城の生徒たちだ。
海城中学・高校といえば、都内では筑波大学付属駒場中学・高校や開成中学・高校、麻布中学・高校に次ぐ男子進学校として知られる。1891年に海軍予備校として創立された伝統校だが、現校長は異色の人材だ。

海城中学高等学校の柴田澄雄校長は三菱商事の出身
柴田校長は三菱商事の出身。鉄鋼輸出部門におり、韓国やサウジアラビア、タイなど海外経験も豊富だ。40年に及ぶ商社マン人生の後、国際教養大学(秋田市)の特任教授となり、グローバルビジネスについて教えていた。
海城は、この四半世紀、3次にわたる改革を推し進め、次はグローバル人材教育に乗り出そうとしていた。両者の接点はそこにこそあった。海城が学校改革をスタートさせたのは創立101年目の1992年。当時は東大合格者が30人を超え、進学校としてブランド化していた時期だったが、なぜ改革にカジを切ったのか。
東大留年率が高い
長年現場で改革に携わった校長特別補佐の中田大成先生は、「海城は『硬派のスパルタ受験校』として東大合格者をどんどん伸ばしていましたが、海城生は他校生に比べ東大に入ってからの留年率が高いという不名誉なご指摘をいただいたりもしていました。要は受験勉強で燃え尽きてしまって、入学した後に持続的に学問・研究に取り組めない。これじゃ建学の精神にうたう『国家・社会に有為な人材の育成』に反する。それで原点に立ち返って人間力と学力をバランスよく兼ね備えた人材を育成しようと、改革を始めたのです」という。
92年を改革元年として、海城中学の入試方式も詰め込み型の知識量を問う問題から論述形式に変え、6年間の教育も一貫して「考える、話す、書く」を基本とすることにした。生徒会やクラブ活動を活発化させ、高校入試を廃止して完全中高一貫制に改めた。30人の帰国子女枠もつくり、多様な生徒を求めた。