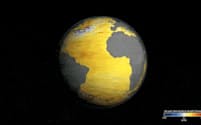解ける南極の氷 今世紀中に海面は1メートル上昇も
西南極にあるパインアイランド棚氷(たなごおり)。その広大な氷原を上空から見下ろすと、表面には大きな亀裂が無数に走る。先端部にできた割れ目は幅が500メートル近い。白い大地がゆっくりと崩壊していく様子を目にしているかのようだ。
パインアイランド棚氷からは、2015年から2016年にかけて面積580平方キロの氷山が分離して、アムンゼン海に流れ出た。この海域の水温は過去数十年に0.5℃余り上昇し、氷が解けて崩落する速さは4倍になった。この棚氷は、アムンゼン海に注ぐ大規模な氷河の一つ、パインアイランド氷河の末端が海に張り出して浮かんでいる部分だ。
西南極氷床と呼ばれるその氷は、面積がフランスの国土のおよそ2倍、厚さは最高で3000メートルを超える。氷が海面下にも分布しているため、西南極氷床は海水温上昇の影響を受けやすい。棚氷が崩壊し、西南極の氷がすべて海に流出すれば、世界の海水面は平均3.3メートル上昇し、世界各地で沿岸部が水没することになる。
パインアイランド棚氷は大半が厚さ400メートルほどだが、1994~2012年の間に平均45メートルも薄くなった。それ以上に気になるのは隣のスウェイツ氷河で、この氷河が崩壊すれば、西南極氷床の大半が不安定な状態に陥るとみられている。
「これらは地球上で最も急速に後退している氷河です」と、NASA(米航空宇宙局)のジェット推進研究所の雪氷学者エリック・リノーは話す。リノーによると、西南極氷床の崩壊はもはや避けられないという。問題は崩壊がいつ起きるか、それに備える時間が人類に残されているかどうかだ。
棚氷は底から解けている
科学者たちは長い間、西南極の氷が急速に解ける可能性に気づかなかった。一つには、船でパインアイランド棚氷になかなか接近できなかったことがある。棚氷の前に広がる海は冬になると氷結し、夏には砕けた海氷が氷山と合体して、バリケードのように立ちはだかる。
1994年3月、米国の砕氷船ナサニエル・B・パルマー号がこの棚氷に到達した。調査の結果、棚氷の下から海面付近に向かって水の流れがあること、その水は周囲の海水よりも塩分濃度がわずかに低いことがわかった。一方、海面下600~900メートルには棚氷の下まで続く海底谷があり、そこを通って、より暖かい海水が棚氷の下に流れ込んでいることも判明した。
海洋学者のスタン・ジェイコブズは、何が起きているかすぐに理解した。暖かい海水は300キロ以上北の南太平洋から流れてくる。この海水は塩分濃度が高く密度が高いため、底のほうに沈み、氷河に向かって傾斜した海底谷を流れる。こうして暖かい海水がパインアイランド棚氷の下に流れ込み、棚氷の先端から数十キロほど内陸にある、氷河と棚氷の境界線(接地線)まで浸入。暖かい海水はここで氷の壁にぶつかって氷を解かし、できた水が海水に混じる。こうして薄まった海水は密度が低いため、暖かい海水の上へと流れ、棚氷の底面に沿って沖に出ていく。
この薄まった海水の量を測定すれば、解けた氷の量がわかる。融解のペースは「とんでもなく速い」と、雪氷学者のエイドリアン・ジェンキンズは話す。彼の計算では、年間53立方キロ(琵琶湖の貯水量の2倍弱)もの氷が棚氷の底から失われているという。接地線付近では、1年間で最高90メートルも氷が薄くなっていると考えられる。
1950年と比べて冬の気温が5℃も上昇
温暖化の影響が最も顕著に表れているのは、南極半島だ。北から流れ込む暖かい空気と海水の影響をもろに受け、半島西側の年間の平均気温は1950年と比べて2.5℃近く上昇した。温暖化のペースは世界のほかの地域より数倍も速い。冬の気温はなんと5℃も上昇した。かつては1年のうち7カ月は海面が氷に閉ざされていたが、今や海氷ができるのはわずか4カ月しかない。
今のところ最も信頼できる予測では、南極の氷の融解により、2100年までに海面が1メートル余り上昇する可能性があるとされている。温室効果ガスの排出削減がどの程度進むかにもよるが、グリーンランドの氷や世界各地の氷河の融解を加えると、2100年までに海面は1~2メートル上昇すると考えられる。
(文 ダグラス・フォックス、日経ナショナル ジオグラフィック社)
[ナショナル ジオグラフィック 2017年7月号の記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。