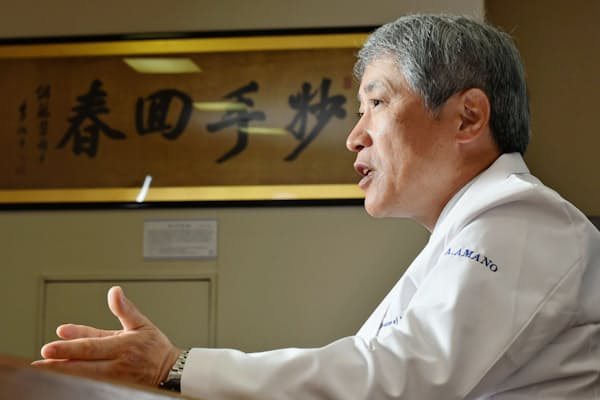宇宙のごみ掃除 「無理」と言われ、逆にやる気に
岡田光信・アストロスケールCEOが語る(下)

岡田光信・アストロスケールCEO
宇宙ごみ(スペースデブリ)を「掃除」するベンチャー、アストロスケール(本社シンガポール)の岡田光信CEO(最高経営責任者、44)が語る母校、甲陽学院(兵庫県西宮市)の思い出。落ちこぼれだった中学時代から一転、高校時代に模擬試験で全国1位をとった岡田少年は、在学中、将来のスペースベンチャー立ち上げにつながる環境問題への関心を深めていった。
<<(上)NASA体験が刺激 甲陽学院の落ちこぼれ、全国1位に
個性的な先生、同級生に囲まれ、多くの刺激を受けた。
高2になると、受験勉強をしつつ、勝手に自分の興味のある分野やテーマを勉強したり研究したりする生徒が結構いました。受験レベルを超えた大学レベルの勉強をする人も多かった。学校の図書館には、そのための本や資料が豊富にありました。
私も高3のときは、趣味で日本史を勉強しました。なぜ「桜井の子別れ」は起こったのか、なぜ阿南惟幾は自刃したのかなど、かなりオタクなテーマを1人で掘り下げていました。模擬試験用の勉強をする以外は、かなりの時間を日本史の勉強に費やしたと記憶しています。
日本史にはまったのは、日本史を面白く教えてくれたとある塾の先生の影響です。授業は毎回ドラマ仕立てで、先生が歴史上の人物になりきり、生徒の前で体を張って演技をするのです。阿南惟幾が自殺する場面では、なぜか、さだまさしの歌をBGMで流し、演じていました。すごく楽しい授業でした。