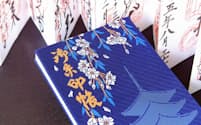『シン・ゴジラ』『君の名は。』に見る新ヒットの法則
日経BPヒット総合研究所 品田英雄

映画界で公開前には予想もできなかったメガヒットが生まれている。怪獣映画「シン・ゴジラ」とアニメ「君の名は。」の2本。この2本に共通するものを探ると、人々が求めている感動の姿が浮き上がってくる。ヒットの法則は今、変化を始めたようだ。
東宝は2016年9月、同年3~8月期の連結業績予想を大幅に上方修正すると発表した。「ドラえもん」や「名探偵コナン」といった定番のアニメ作品が好調だったうえに、「シン・ゴジラ」と「君の名は。」という2つのメガヒットが生まれたことが大きく影響している。17年2月期の連結業績は過去最高となる可能性も出てきた。
「シン・ゴジラ」は「新世紀エヴァンゲリオン」を手掛けた庵野秀明を総監督に迎えて作られた。7月29日に公開され、直後から大人を中心に観客を集め、10月30日時点で興行収入は約79億円と、ゴジラシリーズで最高の数字をたたき出すに至った。

「君の名は。」はアニメファンにしか知名度がなかった新海誠が監督した。高校生の男女が夢の中で入れ替わり……という青春ラブストーリーだ。8月26日の公開以来、10月最終週まで連続9週興行収入1位を記録、興行収入は10月30日時点で約172億円に達している。すでに歴代邦画興行収入で第5位。今後、どこまで記録を伸ばすか注目されている。
「シン・ゴジラ」と「君の名は。」には、これまでの映画には少なかった3つの共通点が見える。
(1)オリジナル=先の読めない物語に驚く
映画界は原作ブームが続いている。「進撃の巨人」「ビリギャル」「海街diary」「暗殺教室」など、出版界で実績のあるものを映像化した作品がヒットしてきた。

だが、「シン・ゴジラ」と「君の名は。」はオリジナル。庵野、新海両氏が自ら脚本を手掛けている。そのため観客はストーリーを事前に知ることができなかった。「シン・ゴジラ」では初めに登場する奇怪な生物が、ゴジラなのかどうかも分からず、観客を戸惑わせた。「君の名は。」では二人の高校生が出会うのか出会わないのか、何をしようとしているのか、その先の展開を予想することが難しかった。
物語とは、本来なら主人公たちはこの先どうなるのだろうという興味をかき立てることが重要なはずだ。それが、実績があったりファンがいたりするということで、原作モノに頼ると見る前に結末はわかってしまう。観客がオリジナル脚本に熱狂する姿は、原作ブームの終焉(しゅうえん)を予想させる。
(2)リアリティー=自分を投影する現実感が楽しい
この2作は現実に忠実な設定をしている。「シン・ゴジラ」では、スタッフが政治家や防衛省関係者に綿密な取材をし、それに基づいて映像化した。会議の場面で官僚たちが大臣にメモを入れる描写や、対策本部が設置されずらりとコピーが並ぶシーンは、多くの公務員に「ウチもそうだ」と共感を呼んだ。「巨大不明生物」という言葉も実際にゴジラが現れたらという取材から生まれた。
また、ゴジラがどのルートを通って東京駅まで行ったのかを地図上で再現したり、自衛隊がどこを通って現場にたどりついたかを調べたりするなど、本来作り物である映画を現実に起こったかのようにして楽しむ人たちが多数登場した。
一方、「君の名は。」には実在の地名や施設が多数登場する。四谷の須賀神社、信濃町の歩道橋、代々木の駅……、アニメなのにどれも実写かと思わせる現実味がある。また、女子高生の暮らす町は特定されていないにもかかわらず、飛騨市の図書館や飛騨古川駅など、同じ光景が広がる場所を見つけ出す情報がインターネットにあふれるようになった。それが実際に場所を訪ねて写真を撮る「聖地巡礼」者を増やす結果になっている。

また、レストランでのアルバイトの裏側、高校生特有の男女の中途半端な距離感の会話など、日常生活をうまく再現していて、若者の共感を集めた。
映画はしょせん作り物。ではあるが、実在する場所、実際に起こりえる行動を再現すると、見る者にこれは本当なのかという気持ちを起こさせる。現実に近ければ近いほど、おもしろくなるという体験を植え付けたに違いない。
(3)リピーター=仕込まれたメッセージを確認したい
2つの映画がロングランになっているのはリピーターの存在が大きい。映画自体にここまで情報が詰め込まれていると、一度見ただけでは理解できないことも多い。特に「君の名は。」の主人公たちの入れ替わったタイミング、二人の時間的関係は複雑にできている。それを確かめに何度も足を運ぶことになる。
また一つひとつのシーンに意味があり、気をつければ気をつけるほど小さなこだわりを見つけることができる。例えば、「シン・ゴジラ」の総理大臣は椅子の後ろに置かれた写真やお札から秋田出身であることも話題になる。
見に行くと毎回発見があり、それをSNSで披露するのも気持ちいい。それに刺激された人がまた、劇場に足を運び、新しい発見をする。こうした循環がロングランにつながっている。一度ですべてがわかる楽しさではなく、繰り返し見る喜びを2作品は伝えている。
オリジナルとリアリティー、それによって生まれるリピーター。これらの3要素は、新しいヒットの作り方の方向を示している気がしてならない。
(敬称略)
日経BPヒット総合研究所 上席研究員。日経エンタテインメント!編集委員。学習院大学卒業後、ラジオ関東(現ラジオ日本)入社、音楽番組を担当する。87年日経BP社に入社。記者としてエンタテインメント産業を担当する。97年に「日経エンタテインメント!」を創刊、編集長に就任する。発行人を経て編集委員。著書に「ヒットを読む」(日経文庫)がある。
日経BPヒット総合研究所(http://hitsouken.nikkeibp.co.jp)では、雑誌『日経トレンディ』『日経ウーマン』『日経ヘルス』、オンラインメディア『日経トレンディネット』『日経ウーマンオンライン』を持つ日経BP社が、生活情報関連分野の取材執筆活動から得た知見を基に、企業や自治体の事業活動をサポート。コンサルティングや受託調査、セミナーの開催、ウェブや紙媒体の発行などを手掛けている。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。