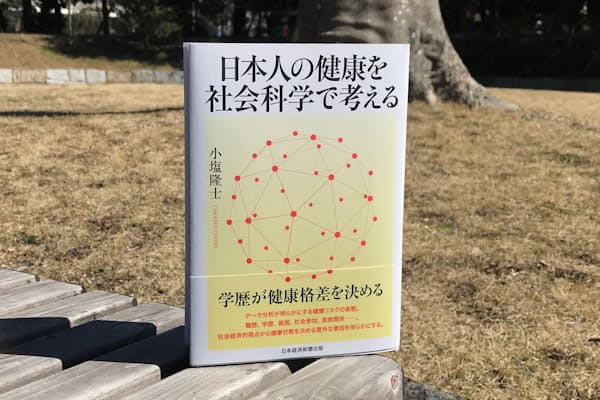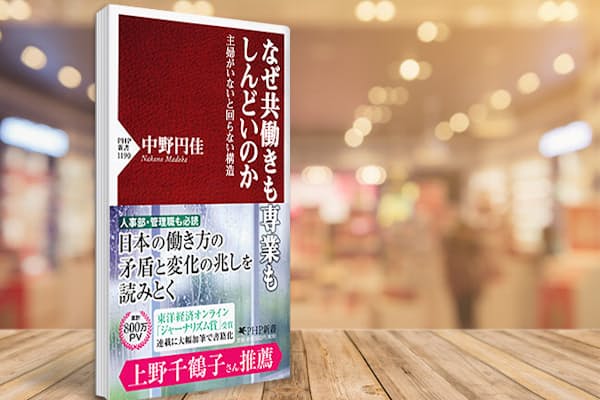保育園に通えない子どもの実態 貧困解決を阻む壁とは
東京都立大学教授 阿部彩

格差が広がる中、子どもの貧困は多角的な視点で解決策を考える必要がある イラスト・よしおか じゅんいち
日本における子どもの貧困の「発見」は2008年と言われ、この年を境に関連書籍が急増し、今も続いている。しかし、「発見」から13年が過ぎた今、求められる書籍の内容は変わってきている。
これまでの書籍は、子どもの貧困の実態を描きだすことが主な目的だった。まだ、子どもの貧困がリアリティーとして信じられないという人が多い時期においては、実態を確たるデータを持って語ることは、政策の必要性を社会に訴えるため不可欠であった。
データ基に分析
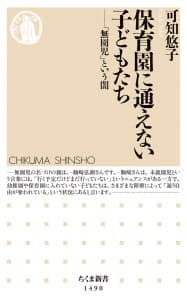
近年に出されたものでは、山野則子編著『子どもの貧困調査』(明石書店・19年)が、データ量・質ともにピカ一である。大阪府の10万人の子どもとその保護者のデータを用いて子どもの生活の各側面(住宅、健康、つながり等)の格差を示している。ちなみに、このような調査は、他の自治体も実施しており、是非、自分の自治体HPで確認して欲しい。また、可知悠子著『保育園に通えない子どもたち』(ちくま新書・20年)は、「無園児」(幼稚園にも保育園にも通っていない子ども)の状況を大規模データとインタビュー調査から描き出している貴重な一冊である。
近年、実態の描写だけではなく、貧困の解決策のヒントとなる書籍も刊行されるようになった。解決策は大きく二分される。一つは、民間や地域の人々の共助によるものであり、典型的には子ども食堂やボランティアによる無料学習塾などが挙げられる。もう一つは、貧困や格差を生み出す社会構造そのものを改善するものであり、これには公の政策転換が必要である。前者は一定の成果を挙げてはいるものの、日本の子どもの貧困を根本的に解決するためには、後者が欠かせない。
ここでは、後者を考える書籍をいくつか紹介したい。まず、教育政策だ。松岡亮二著『教育格差』(ちくま新書・19年)は、幼児教育から高校教育の間に蓄積される様々な格差がいかに子どもを差異化し、学歴格差を再生産しているのかを示し、日本の教育政策の改善を「建設的に議論するための4カ条」を提案する。データに圧倒されるのが嫌な読者の方は、最終章だけでも読まれることをお勧めする。
教育現場で学力格差に対処するためには、入江優子・加瀬進編著『子どもの貧困とチームアプローチ』(朱鷺書房・20年)がお勧めだ。現在、教鞭(きょうべん)をとっている方、これから先生になる方、すべてに読んでいただきたい。