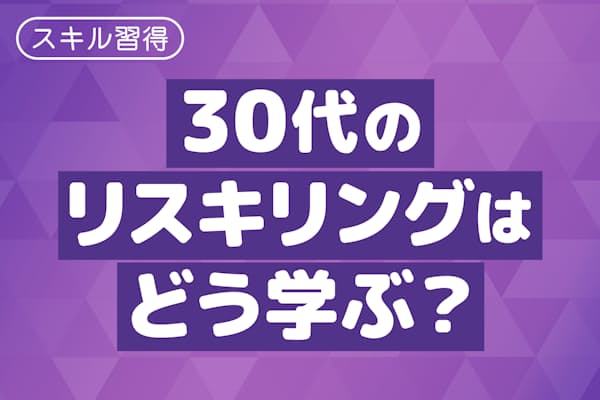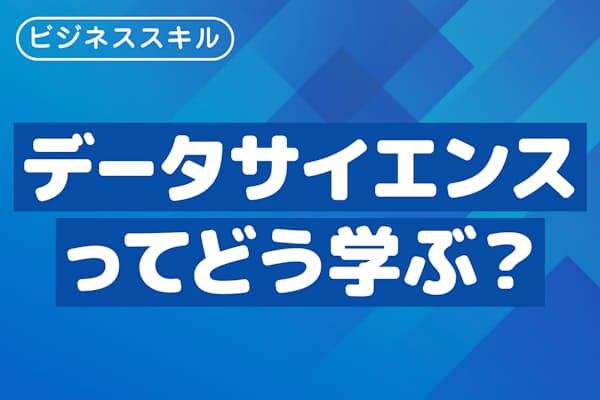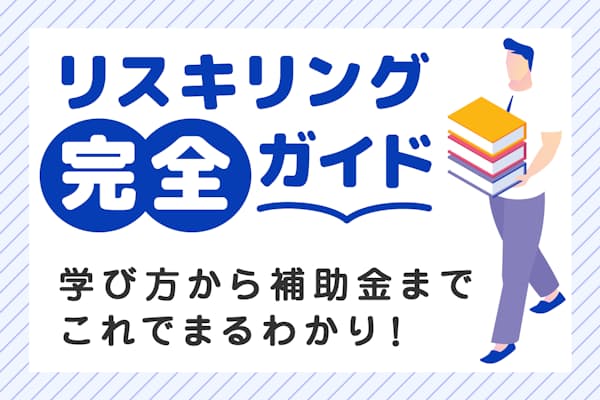若者を失業から守る新卒一括採用 日本の雇用を再評価
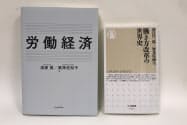
労働市場の仕組みや歴史から説き起こし、「働き方改革」について考察する著作が注目を集める
日本企業はどんな「働き方改革」を目指せばよいのだろうか。新型コロナウイルスの感染が拡大し、労働環境が大きく変わるなか、労働・雇用問題の専門家が、労働市場の仕組みや歴史を説き起こしながら解決の糸口を探る著作が注目を集めている。
濱口桂一郎氏と海老原嗣生氏は共著『働き方改革の世界史』(ちくま新書、2020年9月)で、世界の労働運動や労使関係の歴史を、労働思想の古典とされる文献を紹介しつつ振り返る。個々の労働者が談合し、「人間労力の購買価格」を引き上げようとする「トレード(職種)型」、社内のジョブ(職務)を足場に労働者が権利を獲得していく「ジョブ型」、労使が協調する「パートナーシップ型」や「メンバーシップ型」が生まれた背景や、誕生後の経緯を詳述している。
濱口氏は、どのタイプの労働が中心になるのかは、それぞれの国が置かれた社会事情に依存し、国ごとに全く異なる歴史経路をたどったとの見方を示す。また、欧米では一時、雇用保障が労働者の忠誠心を高める日本型雇用の人気が高まったものの、1990年代以降に日本型は失墜したと指摘し、労働の条件を守り、改善していくための方策を歴史から学ぶよう提唱している。労働経済学者の清家篤氏は「理念と現実、理想と妥協の中で揺れ動く労使関係の本質を見事に描いている」と同書を高く評価する。
清家氏は風神佐知子氏との共著『労働経済』(東洋経済新報社、20年10月)の「守るべきことと変えるべきこと」と題する節で、「人口、技術、市場などの構造変化に対応して雇用のあり方を変革することは必要だ。ただし、そのために日本の雇用制度、労働市場の持っていた強みをなくすことになっては元も子もない」と強調する。日本企業が守るべきことの筆頭は人を大切にする仕組みであり、学校を卒業した若者を失業を経ず直ちに採用する新卒一括採用制度だという。同書は、労働経済学の基本を解説したテキストで、女性や高齢者の雇用、第4次産業革命と労働といった最新の問題も詳しく論じている。
コロナ禍のもとで日本企業の一部では在宅勤務が広がりつつある。在宅勤務に必要なインフラの整備が急務だ、在宅勤務に伴うコミュニケーションロスが大きな問題だとの指摘もある。今本当に必要なのはどんな改革なのか、日本の「歴史経路」を踏まえ、根本から問い直す時期ではないだろうか。
(編集委員 前田裕之)