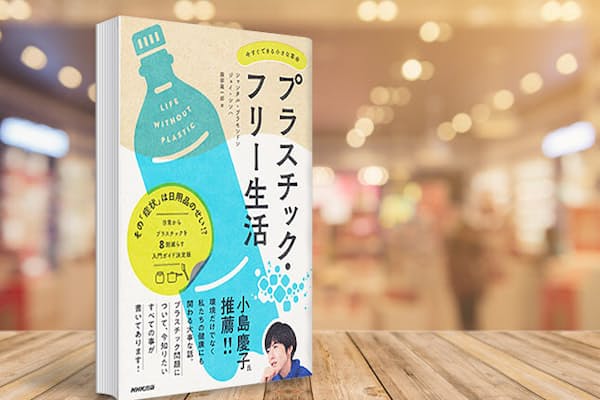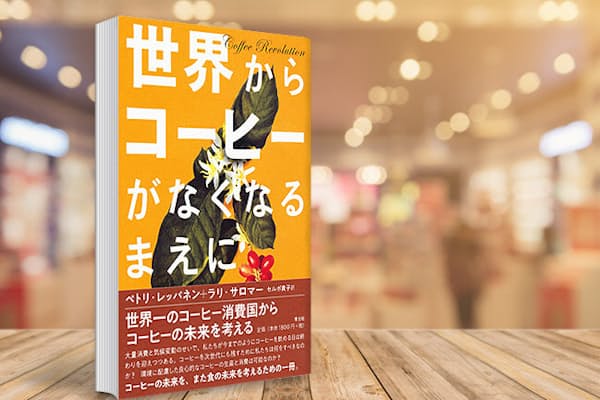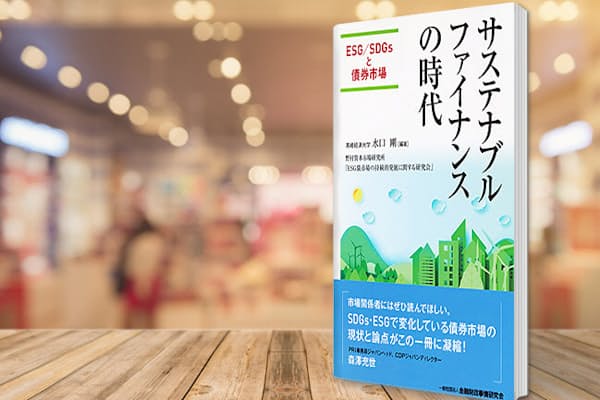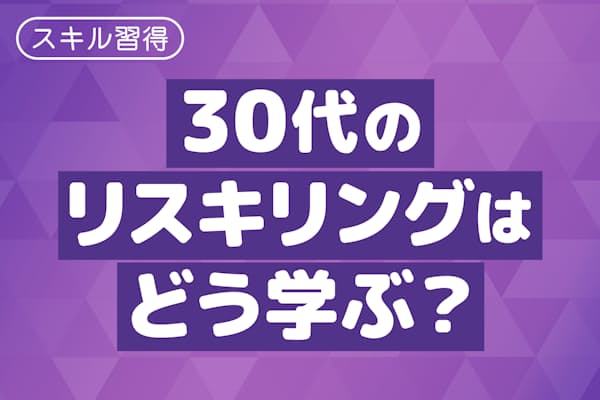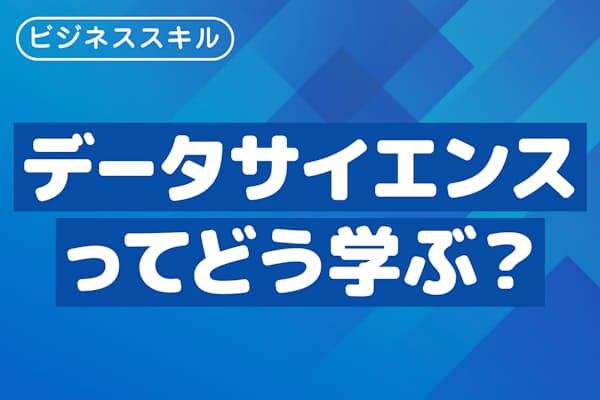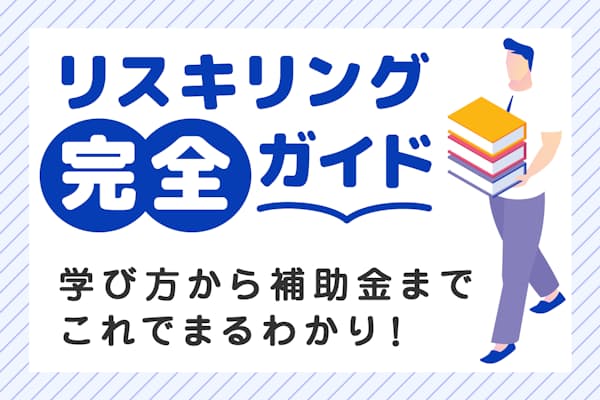生態系壊す海のプラスチックごみ ヒトにも健康リスク
東京海洋大教授 東海正

日本周辺の海域でのマイクロプラスチックの密度は世界平均に比べて1桁高い=イラスト・よしおか じゅんいち
海洋を漂うプラスチックごみ(海洋プラごみ)が地球環境問題として話題となっている。海辺で捨てられたプラスチックストローが海亀の鼻腔(びこう)に入り込み、それを抜き出す痛々しい動画がネット上で広がり、コーヒー専門店がストローの使用を取りやめたニュースや、死んだイルカの胃袋から大量のレジ袋が発見されたとする記事を目にしたことだろう。
2015年の科学雑誌サイエンスの論文によれば廃プラスチック(廃プラ)が年間約800万トンも海洋に流出しているとされ、また50年には海中のプラごみの量が魚の量を上回ることが16年のダボス会議で報告され、いっそう注目されるようになった。この海洋プラごみは15年のG7サミット首脳会合で世界的な問題と認識され始め、以後議論が重ねられて、19年のG20大阪サミットでの目標「2050年までに新たな海洋プラごみ汚染をゼロに」につながる。
プラスチックは軽くて、成形が容易で、かつ丈夫な素材として、生活には欠かせない。丈夫とは言え、海洋プラごみは紫外線によって劣化して波の作用などで壊れて5ミリメートル以下の細かな破片となって環境中に留まる。これがマイクロプラスチック(MP)問題である。
ポイ捨てが汚染に

中嶋亮太著『海洋プラスチック汚染』(岩波書店・19年)は、海洋MPの研究に取り組む若手研究者が最新の成果などを交えながらMPを含む海洋プラごみ問題全般を紹介し、プラごみの多くが日常のポイ捨てや廃プラの不適切な管理から出ていることを伝える。
日本周辺の海域でのMPの密度は世界平均に比べて1桁高いことも調査によって分かっている。MPは今や海中のみならず、それを餌と間違えて誤飲した魚の体内、食卓塩やミネラルウオーターの中、果ては大気中からも見つかっている。MPをヒトが飲み込んでも通常は消化されずに排泄(はいせつ)されると考えられている。ただし、このMPは海洋環境中でPCBやDDTなどの残留性有機汚染物質「POPs」を吸着するとされ、飲み込んだ生物やヒトの体に及ぼすリスクは未解明な部分が多く、研究者が今まさに取り組んでいるテーマでもある。
東京農工大の高田秀重教授が担当した章でMPが生物に及ぼす影響に関して最新の研究成果を紹介している日本環境化学会編著『地球をめぐる不都合な物質』(講談社ブルーバックス・19年)は、MPが海洋中では目に見えずに薄く拡(ひろ)がっている点を挙げ、そのほかのメチル水銀などの重金属やPM2.5などの「不都合な物質」との類似性を指摘しながら、人工的な化学物質の不都合と便益を議論して、この種の問題の深さと解決の難しさを示唆している。