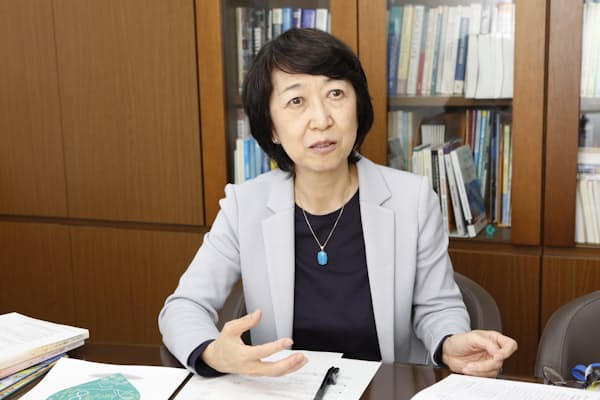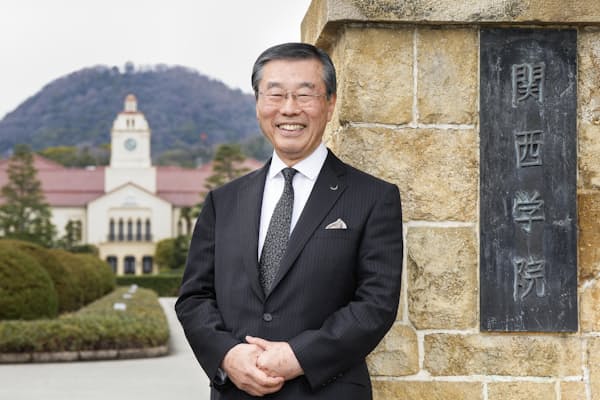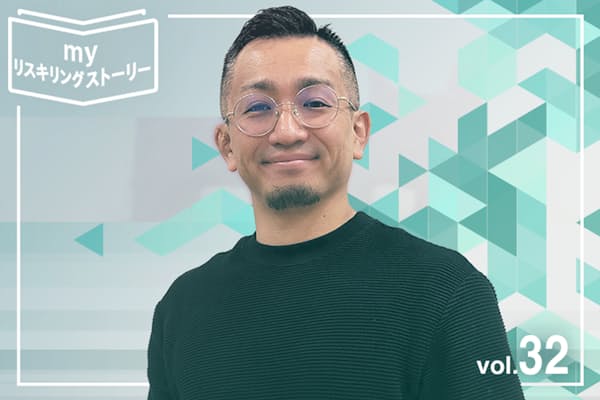安らかな最期を迎えるために がん医療のあるべき姿は
宗教学者 島薗進

患者が主体的に考える社会になりつつある。在宅ケアはその一つの形だ=イラスト・よしおか じゅんいち
がんで死ぬことは死期を悟って生きることだ。恐ろしいことなので患者の心理を考え告知しないという時期が長く続いた。だが、考え方が変わってきた。死に向けて「自分らしく生きる」ことができる、その意味では悪くない事態なのかもしれない。緩和医療が普及し、病む者がどう残りの日々を生きるかを思うゆとりがもてるようになったという要因が大きい。加えて在宅ケアの増加が新たな医療のあり方を拡充している。
こうした新たながん医療のあり方を、若い医師の側も積極的に捉えるようになった。西智弘医師『がんを抱えて、自分らしく生きたい』(PHP研究所・2019年)はこれを「医療の民主化」という用語を用いて述べようとしている。医師が導くのが当たり前と思っていたがん医療から、病む者が自ら考え自ら方向づけて生きていくがん医療への転換が生じているという認識が示されている。
在宅ケアが増加

副題は「がんと共に生きた人が緩和ケア医に伝えた10の言葉」である。たとえば、「このまま病院で死んでしまったら、それは旅先で死ぬようなものだよ」と語った患者がいる。だから家に帰って死にたいといった人の言葉をめぐって、著者は在宅ケアが病む人を自由にさせるのはなぜかについての洞察を引き出していく。病気を治そうとするだけが医療ではないとよく分かる。
『病院で死ぬということ』(主婦の友社・1990年)以来、真にがん患者のためとなる医療を求め、外科医からホスピス医へ、そして在宅医への道を歩んできた山崎章郎医師の『「在宅ホスピス」という仕組み』(新潮社・18年)では、がんを病んで「死を予期して自分らしく生きる」のを支援する医療のあり方の変化が、著者自身の豊かな経験を通して説き明かされていく。
第7章「家で死ぬということ」では05年に活動を開始した「ケアタウン小平チーム」において、病む者が主人公となって最期までを生きていく新たな形が描かれる。そこでは病む者が「家で死ぬ」だけでなく、地域社会が「死にゆく人とともに生きる」ことも視野に入れた試みが取り入れられている。がん医療の新たな試みは、地域包括ケアの好ましい展開につながり、地域社会の変化を促すものともなりうるのだ。