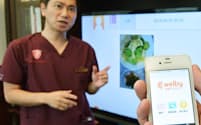血管が裂ける大動脈解離 高血圧に忍び寄る危険
生活習慣改善で予防を
[会員限定記事]
大動脈は体の中で最も太い血管で、心臓から送り出された血液はここを通って全身に行き渡る。この血管が裂けてしまう病気が大動脈解離だ。発症すると直ちに救急車を呼んでも、病院に運ばれる前に亡くなるケースも多い。このため起きてからではなく、できるだけ予防につとめることが大切だ。直接の原因ははっきりと分かっていないが、高血圧などが関係していると考えられている。専門家は「正しい生活習慣を心掛けてほしい」と話している。...
健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。