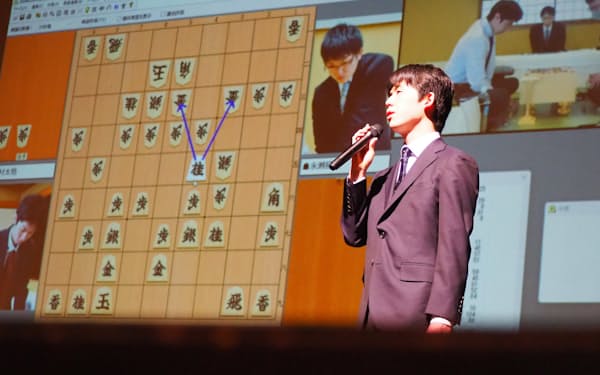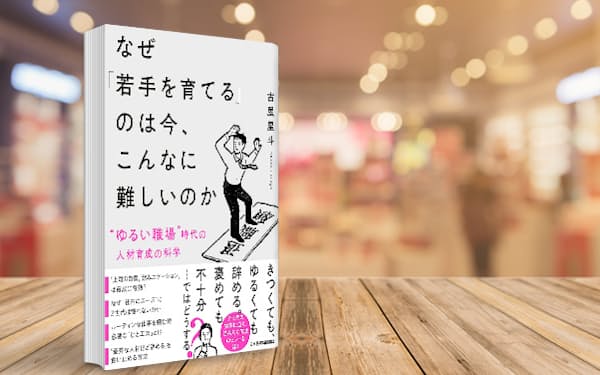外科・内科が連携チーム 心臓病患者に最適治療法
[会員限定記事]
心臓疾患の患者に対し、外科と内科が一緒に協力して治療に当たる「ハートチーム」を結成する動きが医療現場に広がっている。心臓の治療には手術か薬かで方針が分かれることが多く、治療法の選択は大きなリスクと隣り合わせだ。医療技術の進歩などを機に、診療科の垣根を越え、連携。医師は様々な治療法を学べ、患者にとっても、生活の質を上げる最適な治療法選択にも結びつく。
「薬での治療や外科手術には両方とも効果やリスク...
健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。