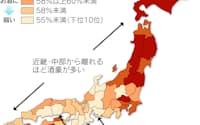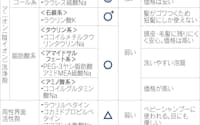日本人の髪の謎 太くて直毛なのにはワケがある
編集委員 小林明
「日本人の毛髪は世界的にかなり特殊な種類に属している」――。最近、こんな話を耳にした。しかも、これは中国や韓国など東アジアに共通する特徴らしい。
そこで、状況を詳しく把握するため、髪の毛の研究に約20年間取り組んできた花王総合美容技術研究所の佐藤直紀室長のもとに向かった。
日本人の髪の太さ 白人のおよそ1.5倍
「日本など東アジア人の毛髪の特徴はとにかく直毛で太いことです。標準的な白人の毛髪のざ...
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。