並木路子 つらい経験、希望の歌に変えて
ヒロインは強し(木内昇)
「リンゴの唄」が流行したのは、戦後まもない頃のこと。焼け野原に響いた少女の歌声に、救われた人も多いという。今の多様な音楽に慣れた耳には、明るさ全開とは言えない曲調なのだが、日々大本営発表の戦況が主に流れてきたラジオから、高らかに澄んだ歌声が聞こえてきたとき、人々は戦争という忌まわしい状況からようやく解放されたと、はっきり思えたのではないだろうか。
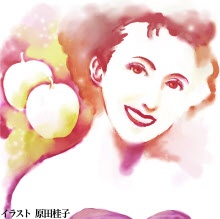
歌い手は並木路子だ。幼い頃から歌が好きで、難関を突破し、松竹少女歌劇に入学した彼女は、戦争終結後すぐ企画が動き出した映画「そよかぜ」の主役に抜擢された。この映画の挿入歌が「リンゴの唄」で、レコード化するなり映画本編をはるかにしのぐ大ヒットとなるのである。
路子はこの頃、二十四歳。その歌声で日本中を元気づけた彼女だが、のちにこう述懐している。「明るくといっても、ほんとうのところ、私はそんなに簡単には明るくなんかなれなかったのです」。路子は戦争で、両親と次兄を亡くしている。こと母親は、三月の東京大空襲で一緒に逃げながら路子だけが助かったため罪悪感が募った。自分の判断で隅田川に入ったから母を死なせてしまったと、後悔が消えずにいたのだ。
初恋の相手だった「ボン」というあだ名の大学生も、兵隊にとられている。陽気で茶目っ気があり闊達な、たいそう魅力的な青年だったらしい。土浦の航空隊に入隊後も、路子がジフテリアで入院したと聞けば、見舞いに訪れるような優しい人である。制服姿があまりに凛々しくて、彼と結婚すると少女は心に決める。だが、ボンもまた帰ることはなかった。特攻隊として若い命を散らしたのだ。ボンが忘れられず、路子はその後長く独りでいる。あの戦争にはこうした悲恋が、数限りなく潜んでいるのだろう。
親しい人の死に浸る間もなく、歌劇団に所属していた路子は、外地に駐屯する日本軍の慰問に赴く。戦地秘匿のため幌を被せたトラックに乗せられ、中国の奥地へ向かうのは不安で過酷な行程だったろう。が、兵隊さんたちが懐かしがったり喜んだりするのを見ると、苦労も吹き飛んだと彼女は言うのだ。
歌や芝居、映画や小説といった文化は、危急の折にはまっさきに統制される。確かに、医療や食糧のように必要不可欠なものとは言いがたい。が、娯楽がなければ世界は貧しく殺伐としたものとなるだろう。戦争直後の食糧も行き渡らない時代、人々は喉の渇きを潤すように映画を観、活字を求め、歌を聴いた。そうやって心を満たし、明日へと挑んでいったのである。
並木路子の歌声は、多くを失った人々に、これから先も道は続いていることを伝えた。そしてその道は、暗く悲しいばかりではなく、明るい希望をはらんでいることを。それがかなったのは、生来の歌の資質だけではないだろう。路子自身が過酷な経験を乗り越えてきたからこそ、焼け野原を希望の灯りで照らすことができたのだ。
[日本経済新聞朝刊女性面2013年11月23日付]

※「ヒロインは強し」では、直木賞作家の木内昇氏が歴史上の女性にフォーカス。男社会で奮闘した女性たちの葛藤を軽妙に描きます。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。
関連企業・業界









