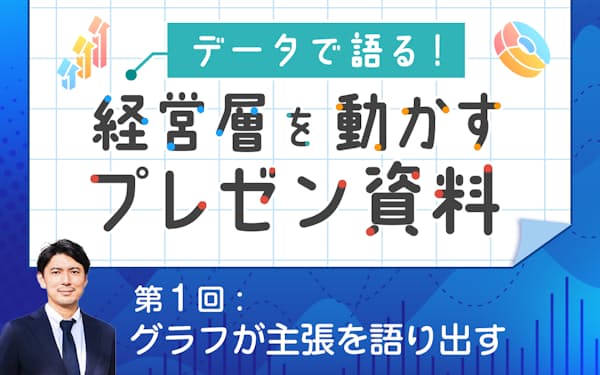未入籍でも「婚姻の意思あり」 事実婚のメリットは

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの前野彩です。早速ですが、クイズです。
Dreams Come Trueの吉田美和さん、後藤久美子さん、萬田久子さん。この3人の芸能人に共通することは、なんでしょう?
この3人に共通するのは、「事実婚」をしている(していた)ということです。実は私も2000年からずっと事実婚をしています。
事実婚とは?
事実婚とは、当人同士の意思で入籍はしないけれど、社会的には入籍をしている夫婦と同様の状態にある2人のことをいいます。簡単にいうと、入籍していない夫婦のことですね(既に結婚している人が愛人を作って……という関係ではありません。念のため)。
「同せいとどう違うの?」とよく聞かれますが、同せいは、今、一緒にいたくて生活しているだけなので、社会的な信用度は低いのが現状です。でも事実婚は同せいと異なり、法律婚に準じて法的に保護される部分もありますし、夫婦として利用できる制度もあるのです。
同せいとの違いはどう証明するか
事実婚を証明する手段は、住民票です。
同せいの場合は、そもそも住民票を移さない人が多いでしょうし、移す場合も「同居人」という続柄で提出するのではないでしょうか。あるいは、それぞれが世帯主となって同じ住所に住民票を作ることでしょう。
余談ですが、年末近くなると会社に提出する年末調整の書類に、世帯主を記入する欄があります。彼と住むことになって住民票を移すけれどそれを知られたくない場合、同居人ではなくそれぞれが世帯主になればいいでしょう。
さて、同せいと事実婚の違いに戻ります。
入籍すると、住民票の続柄記載は、「世帯主」、世帯主以外の続柄には「妻(または夫)」と記載されます。
事実婚では、夫が世帯主なら妻は「妻(未届)」と記載できるのです(夫の場合は「夫(未届)」)。この記載があると、単なる異性の同居とは違い、婚姻の意思はあるけれど、婚姻届を出していない関係という証明ができますね。
現在の民法では、婚姻届を提出するときには、夫婦どちらかの姓を名乗らなければならないのですが、多くの場合、女性が男性の姓を名乗ることが慣例になっています。そのため、仕事をする女性にとっては実務的な不利益が発生したり、精神的な負担となったりすることもあります。これを改善すべく、2015年には最高裁まで争われましたが、夫婦がどちらかの姓を名乗ることは合憲とされました。ただし国連からも勧告を受けているので、今後は夫婦別姓も法律で認められるようになる可能性はあるかと思います。
事実婚のメリットは
私が事実婚をしていることを伝えると、興味を持って話を聞いてくださるのは圧倒的に女性です。そして、結婚や離婚を経験された方の中には、「そんな方法があると知っていたら、最初から事実婚したかった」とか「次は絶対に事実婚!」とおっしゃる方もいます。
リップサービス的な発言もあるでしょうが、次の「現実的な労力」を経験してこられた人には、事実婚は女性にとってこれらの労力のほとんどが不要という実務的なメリットはあるようです。
<入籍に伴って必要となる手続きの例>
・戸籍の届出
・住民票の届出
・印鑑の作成
・銀行や証券会社などの金融機関の氏名変更、キャッシュカードの変更手続き
・保険の契約者、被保険者の氏名変更、受取人の変更
・パスポートの氏名変更
・保有資格の氏名変更
・自動車免許など各種免許の氏名変更
・クレジットカードの氏名変更
・携帯電話の名義変更
・健康保険、厚生年金などの氏名変更
・職場や友人などへの結婚報告
・勤務先での氏名変更
いろんな変更作業があるからこそ「夫婦でこれから生活していくんだ」と認識を新たにするという一面もあるでしょう。ただ、姓の変更とそのための作業が一般的には女性に偏っていることからも、夫婦別姓や事実婚に対する女性の関心が高いのが現状です。「結婚しなきゃいけないの?」「入籍しなきゃいけないの?」と、疑問が出てきたときに考えてみてはいかがでしょうか。

Cras代表取締役。FPオフィス will代表。大阪在住のファイナンシャル・プランナー。中学校・高校の保健室の先生を経て、結婚、退職、住宅購入、加入保険会社の破たんを経てFPに転身。自らの 住宅ローンで800万円、生命保険で1000万円の見直しを行った実績を持つ。講演やテレビでも活躍中。著書多数。新著に『本気で家計を変えたいあなたへ ―書き込む"お金のワークブック"』(日本経済新聞出版社)、『家計のプロ直伝!ふるさと納税新活用術』(マキノ出版)、『危うくムダなお金を払うところでした』(産経新聞出版)。
[nikkei WOMAN Online 2016年4月18日付記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。