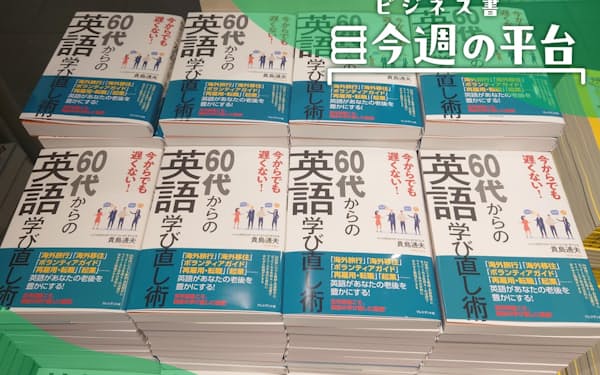有安杏果 手が小さいと陶芸も楽器もホントに不便
ももクロVS伝統工芸/有安杏果、「笠間焼」に挑戦(2)

アイドルグループ、ももいろクローバーZのメンバーが、日本の伝統工芸に挑戦している連載「ももいろトラディショナル」。今回は「ももクロの小さな巨人」有安杏果さんが陶芸に挑戦する第2回です。有安さんが訪れたのは、関東随一の歴史を持つ「笠間焼」の伝統と技術を伝える茨城県立笠間陶芸大学校。ろくろの上の粘土を操り、人生初の陶芸作品を作ることができるのでしょうか? 【第1回はこちらから】
「まずは土殺しから」「え、土殺しって何?」
第1回では、陶芸を教えてくれる陶芸大学校の生徒さん3人と対面し、笠間焼の歴史から「土を作る」ところまで学んだ有安さん。今回は、粘土を焼きものの形にしていく「成形」の体験。有安さんが「テレビで見たことある!」というろくろで、飯わん作りに挑戦します。
「失礼しまーす」と有安さんが入ってきたのは、陶芸大学校の実習室。生徒さんたちが陶芸の技術を学び、卒業制作などの作品づくりを行う場所です。

今回、有安さんに陶芸を教えてくれる、1年生の弓野しおりさんがろくろの前に座ります。
弓野さん まず最初に、土殺しという作業をやっていきます。
有安さん え、土殺しって何?
「土殺し」とは、窯で焼いたときに割れたりヒビが入ったりしないよう、粘土の中に入っている空気を抜き、ろくろに土をなじませる作業。弓野さんがお手本を見せてくれます。
手にどべ(水と粘土が混ざった泥状のもの)を付け、ペダルを踏んで電動ろくろを回し始める弓野さん。回転台の上のこんもりとした粘土が、グルグルと回転します。そのこんもりした粘土が、弓野さんが手を添えるとみるみる上に伸びて、細長い円筒形に。それをすぐに押さえ込み、もとのこんもりした形に戻して、また円筒形にひき伸ばします。伸びたり縮んだり、手品のように変形する粘土に、「すごく不思議なんだけど!」と驚く有安さん。

弓野さん 大事なのは、芯をまっすぐに立てていくことです。芯がまっすぐになってないと、このあと、モノを作るときに形がブレちゃうので。
続いて見せてくれたのは「土取り」。土殺しした粘土にくびれを付けて、作品に必要な量の粘土を用意する作業です。
ろくろを回しながら両手で粘土を包み、指の腹を使って、くびれを作る弓野さん。これが土取りのようです。

そのままの流れで、弓野さんは飯わんの成形まで進んでいきます。

有安さん すごーい!
みるみる飯わんの形になっていき、目を輝かせる有安さん。
弓野さん ああ、緊張してちょっと失敗しました(笑)。このあとヘラなどで均等にならして、口が当たる部分をきれいにし、くびれの部分から切れば完成です。
さらりと話す弓野さんに、「無理だと思う!」と完全に弱気モードの有安さん。
有安さん できないよ! 私、手、小さいし。
弓野さんの隣で見ていた、1年生の大和田友香さんが「手が小さいと、けっこう難しいです」と相づちを打ちます。
有安さん まただよ。手が小さいと、何にもできない。楽器もできないし。もう、ホント不便(笑)。

指でつまみながら上に伸ばすように……
土取りまでは弓野さんや大和田さんがやってくれることになり、有安さんは飯わんの成形に集中することになりました。ろくろの前に座り、ペダルを踏んで電動ろくろを回す有安さん。
有安さん 回す速度は、どのくらいがいいんですか?
弓野さん ペダルを踏み込むほど速くなるので、自分のちょうどいい速さで。
有安さん ちょうどいい速さ……。それがわからないから(笑)。
「もうちょっと早い方がいいかな」など生徒さんたちにアドバイスをもらいながら速度を定めます。まずは底となる部分をおおまかに作る「底を取る」という作業からスタートです。
大和田さん 小指をくびれに当たるようにして支えながら、親指で粘土の真ん中をちょっとずつ下に押すと、穴が開いてドーナツ状になっていきます。まずはそこまで。



言われた通り、有安さんが親指で土を押していくと、円筒形の真ん中がくぼんでいき、ドーナツ状になりました。
有安さん もう、親指を抜いても大丈夫?
大和田さん はい、もう大丈夫です。水がなくなると滑りが悪くなるので、一度、手にどべをつけていただいて。ドーナツの穴みたいなところにも、ちょっとどべを入れていただいた方がいいかもしれない。
手にどべをつけ、穴を湿らせる有安さん。
大和田さん そうしたら、次。親指を横にスライドする感じで、穴をどんどん広げていきます。
有安さん え……こう?
大和田さん ああ、そうですそうです。
口の広い湯飲み茶わんのような形に変形していきます。

大和田さん もうちょっと親指と手のひらでしっかり挟んで、つまみながら上に上げていく感じで……。
有安さん こういうこと?
大和田さん そうです、そうです。そうしたら次は、右手をキツネのような形にして、中指と親指で土を挟んで。挟んでいる指の力で、どんどん上に土を伸ばしていきます。

言われた通りにしますが、なかなか上に土が伸びません。大和田さんに「もうちょっと力を入れて」と言われ、有安さんが指に力を入れると……力が入りすぎたのか、せっかく作った形が崩れていきます。
有安さん うわわっ、助けて!

すかさず大和田さんがサポートし、もとの形に戻りました。「助けてもらった~」と安堵する有安さん。もう一度、キツネの手でトライしますが、またしても形が……。
有安さん あっ、やばい! 助けてー!
大和田さんがヘルプします。
有安さん ……難しい。すぐ形が崩れちゃう。
大和田さん 難しいですよね。もうちょっとゆっくり、土をつまんで薄くしていく感じでやってみましょう。
近くにいた陶芸大学校の尾形尚子先生が助け舟を出します。
尾形先生 指でまっすぐ上に持ち上げる感じですね。ろくろと一緒に手が回っちゃうと、「助けて!」になっちゃいます。
どうやらろくろの回転に、指の力が負けてしまっているようです。
「教えるのって難しいな……」
それから何度かトライしますが、うまくいかない有安さん。いま一度、先生にお手本を見せてもらうことにしました。
有安さん 今度は石川くん、教えて。出番だよ!

本日の唯一の男性コーチ、1年生の石川晃平くんが登板。ろくろに手を伸ばします。
石川くん キツネの手をして、ここらへんを挟みます……。
説明が難しいようで、言葉が続かない石川くん。感覚的な作業のため、大和田さんも弓野さんも、どう教えたらいいのか困っている様子です。
大和田さん 難しいな。教えるのが難しい……。
手取り足取りサポートしてもらいながら、なんとか有安さんの飯わん成形ができていきました。とりあえず一安心ですが、まだ土のかたまりから飯わんを切り離す作業が残っています。
できあがった飯わんを切り離すのも一苦労
ろくろからできあがった飯わんを外すには「シッピキ」と呼ばれる糸を使います。この糸でろくろから切り離すのです。

尾形先生 糸がくびれに絡まり、一周したら……引っ張る!
何度かやってみますが、切れません。諦めず、「もう1回だ」と有安さん。糸は食い込んだのですが、スッパリと切り離せず、せっかく作った飯わんが崩れ落ちそうになります。

有安さん 助けて、晃平くん!
石川くんが落ちそうになった飯わんをキャッチ!
有安さん ナイスキャーッチ!!

しかし形が崩れたため、もう一度、はじめからやり直すことにしました。昔から職人たちの間では「土練り3年、ろくろ10年」と言われたそうです。そうそうたやすくないからこそ、面白いものなのかもしれません。
気分も新たに、ろくろの前に座った有安さん。さあ、今度こそ有安杏果作の飯わんは完成させられるのでしょうか?

【第4シーズン】有安杏果VS笠間焼(茨城県)
第1回 笠間焼に挑戦 絶対崩れちゃいそう
第2回 手が小さいと陶芸も楽器もホントに不便
第3回 「ああ、めっちゃムズい」 心が折れそう
第4回 詞やメロディーを考えるときは本当に苦しい
最終回 失敗がおしゃれに見えるってやばい!
【第1シーズン】佐々木彩夏VS越前漆器(福井県)
【第2シーズン】玉井詩織VS万祝(千葉県)
【第3シーズン】高城れにVS江戸切子(東京都)
百田夏菜子、玉井詩織、高城れに、有安杏果、佐々木彩夏で構成されるアイドルグループ。2008年5月に結成(当時のグループ名は「ももいろクローバー」)。観客数十人の路上ライブからスタートし、わずか6年で国立競技場ライブを実現。大会場のコンサートと並行して、小さな会場でのライブやユニークなイベントなども積極的に企画、ファンを驚かせ、楽しませている。12月23日、24日は恒例の『ももいろクリスマス2016 ~真冬のサンサンサマータイム~』を幕張メッセ(千葉市)で開催する。
有安杏果
1995年3月15日生まれ。埼玉県出身。幼少期から子どもタレント、キッズダンサーとして活躍。2008年、中学1年生のときにスターダストプロモーションにスカウトされる。09年に、ももいろクローバーへ加入し、現在に至る。イメージカラーは緑。2016年には横浜アリーナで1万人規模のソロ・コンサートを成功させ、楽曲制作にも携わったミニアルバムも発表した。来年の6月から7月には東名阪3会場で初のツアーを行う予定。
デビュー当時のコンセプトが実は「和をモチーフにしたアイドル」だった彼女たちが、日本の伝統工芸を学ぶ連載。メンバーが伝統工芸の仕事現場を訪れ、作る過程を勉強し、実際にもの作りを体験。さらにその道で頑張っている同世代の若者と夢や目標を語り合うという詰め込みすぎな企画です。
(文 泊貴洋/写真 中川真理子/ヘアメイク 谷川一志=kind/企画協力 佐々木健二=ジェイクランプ)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。