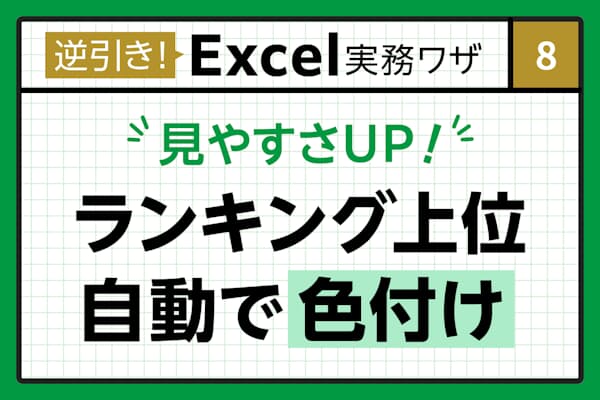ゆとり世代の「やる気スイッチ」を入れる方法
早稲田大学研究戦略センター教授 枝川義邦氏

PIXTA
五月病、理由のひとつに「世代間の感覚の違い」
――五月病は昔と今で症状が異なったり、相対的に増えたりしているのでしょうか。

早稲田大学研究戦略センター教授の枝川義邦氏
五月病は、新しい環境になじめずに、やる気や自信を失い、なにをするにも面倒くさいなどの精神的な症状や一日中だるくてたまらないといった身体症状を呈するものです。医学的には「適応障害」と呼んでいます。かつては神経症という呼び名もありましたが、現在では適応障害でくくられているので、症状も専らその範囲に含まれるものとされます。厚生労働省の統計によると、適応障害で実際に医療機関にかかった患者数は、実はこの20年でさほど増えてはいません。
―――「ゆとり世代」など20歳代の若手社員のやる気が足りないとか、精神的にまいっているというケースはよく聞きますが。
その理由のひとつには、世代間の感覚の違いがあるといわれます。五月病は若い世代に多いように感じるのはそのためです。新しい環境では、職場の環境として、仕事する場所やそこで働く人々、仕事の内容がこれまで慣れ親しんだものと違うことになりがちです。とくに、自分の周囲の人たちとのコミュニケーションを通して自分の就業環境をつくっていくという状況に適応していくことが求められることが多いものです。
これを「ハードルが高い」と感じてしまう、つまり、コミュニケーションを含めた適応がうまくできずに、その環境をストレスに感じてしまうケースが若い世代で多くみられることが世代間の意識の違いとして露呈している、というのが現況でしょう。
最近では「レジリエンス(回復力)」という心理学用語をよく耳にします。なにか精神的なストレスを受けて気分が大きく沈んでしまうような状況でも、それを受け入れて回復させていく「心の柔軟性」のようなものですが、これが十分に働かないと、新しい環境に適応できずにうつ状態になりやすいのです。「ストレス耐性」として考えられていますが、ストレスを跳ね返すというよりは、いちど受け入れた後の反応が「柔軟である」と言った方がイメージに合います。
新しい環境で自分の常識が通用せず、適応障害に
レジリエンスは、相手の多様性を認めたコミュニケーションを取っていくことで鍛えられるものなので、自分が育った環境でどのようなコミュニケーションを取ってきたかによっても異なります。まさに、どの程度の「耐性」をもっているのかに多様性があるのです。このような適応障害は例えば、かつては「気合が足りない」といった精神論でどうにかなっていた部分もありますので、そのような経験を積んできた人生の先輩方にとっては、若い世代の甘えのようにも映りがちです。
善かれあしかれ周囲とのコミュニケーションを強いられた世代には歯がゆく感じることでしょう。しかし、実際に人間同士でのリアルなコミュニケーションを取らなくても十分な環境で育った世代からすると、いきなり新しい環境に置かれることは、自分の常識に合わない状況が起きているのです。至極当然のことですが、自分の常識にあった対応を精いっぱいしていても、うまく適合できずに、ストレスがたまってきてしまうという事態になっているのです。逆に、そのような状況を認めないとならない昨今の職場環境では、世代の異なる人材にどのように接してよいのか分からず、年上世代の方が困惑して精神的に参ってしまう例もあるようです。
年上世代がダイバーシティーと覚悟を決め、「適応」を
そうなると、ゆゆしき問題が浮き彫りになっていきますが、これも最近、声高にうたわれる「ダイバーシティー(多様性)」の一環だと覚悟を決めて、現況に「適応」していくことも、年上世代のレジリエンスのひとつです。
ダイバーシティーには、国籍や性別の多様性を受け入れることの重要性だけでなく、文化的背景や世代間の差異などの多様性があることも当然のこととして成り立つコミュニティーや人間関係を含んでいます。それは、すでに多くの職場でも起きている事態であり、極めてドメスティックな企業であっても、日本人だから画一的な発想をするという常識は通用しなくなっているのです。上司にあたる年上世代も、世代間の差異は多様化の訪れであることを認めていただき、対立や善悪の決着をつけるのではなく、共存する環境づくりを心がけるのがよいでしょう。
――どうすれば上司は若手社員の「やる気スイッチ」を入れられるのでしょうか。
やる気とはモチベーションのことですから、なにか行動を起こすためのスイッチになるものです。モチベーションは、なにかをしたい、手に入れたいという欲求から生じるものなので、その欲求により、やる気のスイッチが入る場面が異なってきます。
すると、現代のように多様な欲求を持った人材が集まる社会では、やる気がでるスイッチも多様だと言わざるを得ません。
人間が欲求をもつ目的のひとつは、それが満たされたときに感じる満足感を得ることでしょう。なにかを手に入れたときや、周囲に認められたとき、自分が設定した目標を達成したときなど、自身の求めたものごとに応じてそれぞれの満足感が得られます。
それぞれ異なる「ご褒美」のポイント
満足感とは文字通り気持ちが満たされることですが、このような状況は、脳にとっても「報酬」、すなわちご褒美になっています。とくに、その欲求が満たされると予想できるときには、脳のなかで「報酬系の神経ネットワーク」の活動が高まります。すると、神経伝達物質「ドーパミン」が多くなり、それを喜びに感じたり快感を覚えたりするのです。この感覚を得るために、脳ではやる気が生じる、といっても過言ではありません。
欲求の多様性とは、このような脳のなかで報酬に感じるためのスイッチが多様であることを指します。個々人がもつ「ご褒美」のポイントがそれぞれ異なるので、やる気のスイッチを入れるためには、その欲求を知ることが必要です。
目の前に「ご褒美」にあたるインセンティブをぶら下げても、それに対しての魅力を感じなければ、気持ちも身体も動き出しません。魅力を感じるかどうかは、その本人の欲求に即しているかが重要なので、厳密には、インセンティブを設定するときに、個々人の欲求の本質を把握しておかなければならないことになります。
となると、個々人の欲求が多様である現代では、同じニンジンでは効果が薄いことは容易に予想されることです。職場での振る舞いだけが自分の人生を左右するわけではないとなると、それにどれだけ注力するかという個人のもつ能力やスキルといった資源の配分の比重が低くなるのは当然の流れといえます。
「ハードル」下げた成功体験で「やる気スイッチ」

五月病にかかった相手の「やる気スイッチ」を入れるには、そのひとを「その気」にさせるのも良い手だと思います。ここでいう「その気」とは、「セルフエフィカシー(自己効力感)」と呼ばれるもので、目の前の「ハードル」を自分が飛び越えられるかどうかについての自信のようなものと解釈されています。
いくら「やる気をだせ」とたきつけても、その本人の「その気」が上がらないと、言った側も言われた側も、空回りしてしまいます。セルフエフィカシーとは結果が出せることを信じる心理的な尺度なので、自身の成功体験や身の丈に合った励まし、成功者としてのロールモデルの存在が大きく影響します。
やる気がでずに失敗が続いたりするときには、成功体験を積むために、仕事などの「ハードル」を下げて、きちんとこなせる状態をつくるのがよいでしょう。たとえ小さなものであっても、それを成功体験とできれば、脳の報酬系も動き出します。エンジンがかかったら、ハードルを上げていけばよいのです。また、セルフエフィカシーには、体調や気分も影響するので、疲れをためないことや気持ちの切り替えができる環境づくりも大切になります。
(代慶達也)
早稲田大学研究戦略センター教授(早大ビジネススクール兼担講師)。1969年生まれ、東京都出身。98年東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了、博士(薬学)。2007年早大ビジネススクール修了、MBA(経営学修士)。同年、早大スーパーテクノロジーオフィサー(STO)の初代認定を受ける。14年から現職。脳の神経ネットワークから人間の行動まで、マルチレベルな視点による研究を進めており、経営と脳科学のクロストークを基盤とした執筆や研修も行っている。著書に『「脳が若い人」と「脳が老ける人」の習慣』(明日香出版社)、『記憶のスイッチ、はいってますか』(技術評論社)、『タイプが分かればうまくいく!コミュニケーションスキル』(共著、総合法令出版)など。