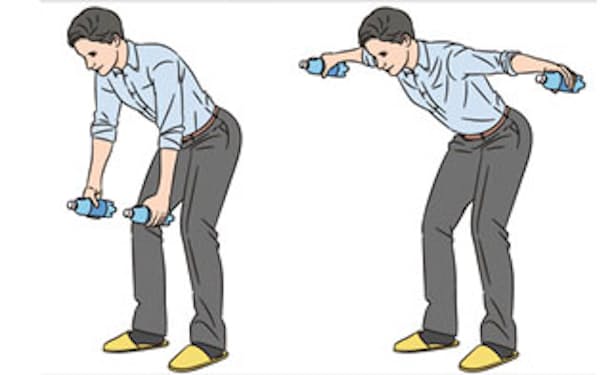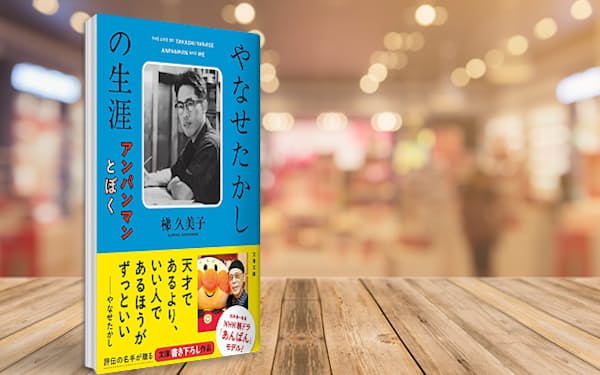「面白い作品、もっと知って!」 マンガ大賞を設立
吉田尚記(ニッポン放送アナウンサー)

「マンガを肴(さかな)に酒を呑(の)みたい」「面白いマンガを誰かに薦めたい」。そんな思いから出発した「マンガ大賞」が、今年も29日に発表になる。ニッポン放送アナウンサーの私が発起人となり、書店員を中心にした有志がボランティアで運営している手作りの賞だ。
賞を立ち上げるきっかけは、私がパーソナリティーを務める、音楽とマンガをテーマにしたラジオ番組「ミューコミ」(現・ミューコミ+プラス)だった。もともとマンガは大好き。もっと勉強しようと書店巡りを始め、多くのマンガ好きの書店員さんと仲良くなった。
彼らと話すうち「マンガの世界には読者寄りの賞がない」ことに気付いた。小説には既に「本屋大賞」があったのに。
★ ☆ ☆
既刊8巻までが対象
「面倒」「やったところで得などない」。賞がない理由はそんなところだろう。だが、好きでやるなら面倒とは思わないし得をする必要もない。2007年夏、参院選の某候補者の事務所に取材に向かう途中で思いつき、親しい書店員さんに電話をかけたのを鮮明に覚えている。
趣旨に賛同してくれた8人で実行委員会を作った。メンバーは書店員4人にデザイナー2人、イベント屋さん1人に私。すごい人ばかりで、当初は皆さんの仕事の早さに驚くばかりだった。
選考対象の規定には気を遣った。何十巻も続く作品は有名だし、読むのが大変で一般の人に薦めにくい。実行委員と書店で本棚を眺め、最大8巻まで刊行されている作品を対象と決めた。マンガは、人気がなければ連載が打ち切られる厳しい世界。9巻以上ある作品は、その事実だけで面白さが保証されているようなものだ。
★ ★ ☆
選考員選びは公平に
賞は100人程度の選考員の2度の投票で決める。選考員は皆、実行委員の誰かの何らかの知り合いだ。不思議なもので、本当にマンガが好きな人は会って話すとすぐ分かる。書店員以外にも教師、主婦など経歴は様々。フリーアナウンサーの松尾翠さん、ロックバンド「PENICILLIN」のHAKUEIさんなど有名な方もいる。
公平のため、利害関係が生じかねないマンガ家や編集者、ブックデザイナーは選考に参加できない決まり。賞のロゴマークを無償で作ってくれたブックデザイナーの関善之さんにさえ投票してもらっていない。実行委員の一人である書店員も、その後編集者に転職したため投票していない。
投票はネットで行うのでパソコンで集計してもいいが、それではつまらない。すべて印刷してニッポン放送の会議室で一つずつ読み上げ、ホワイトボードに「正」の字を書くスタイルを今も続けている。もちろん読み上げはアナウンサーの私。大勢の選考員とハラハラしながら見守るこの時は最高に盛り上がる。
えたいの知れない賞を受け入れてもらえるだろうか。08年3月、第1回の発表の時は不安で仕方なかった。そんな中「岳」で初の大賞に輝いた石塚真一さんは授賞式に快く出席してくれた。本当にありがたかった。
続く第2回の「ちはやふる」(末次由紀著)から昨年の第8回「かくかくしかじか」(東村アキコ著)まで、毎回素晴らしい大賞作が選ばれた。「テルマエ・ロマエ」で第3回大賞となったヤマザキマリさんが海外にいて、テレビ電話で授賞式会場とつなごうとしたが直前までうまくいかず右往左往、などドタバタ続きではあったが。
正直に言えば、1次選考で大賞ノミネート作を選んだ段階で私は満足なのだ。今年も素晴らしい11作がそろった。ギャグと恋愛とか、比べようがないのは十分わかっている。2次投票での順位決めはあくまでお祭り。興味のある人は、大賞作以外も手にとってほしい。
★ ★ ★
全てボランティア
賞運営の苦労といえば、やはりお金がないことだ。サイトのデザインから授賞式の企画・運営・司会まですべてがノーギャラ。選考のために読む80冊ほどのマンガも自腹だ。ビジネスとしては全く成り立っていない。

だが、好きだからつらいと思ったことは一度もない。大賞作が受賞後に売り上げを大きく伸ばすなどインパクトを持つようになったのも、ビジネスと無関係な純粋なマンガ愛ゆえだろうか。
毎年、授賞式を終えて一段落した5月に、関係者の打ち上げを開いている。ここではマンガに出てくる料理「マンガメシ」を食べるのが恒例。マンガを愛する仲間と、マンガを肴に酒を呑む。賞はこの日のためにやっているようなものだ。
(よしだ・ひさのり=ニッポン放送アナウンサー)
[日本経済新聞朝刊2016年3月24日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。